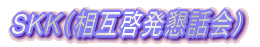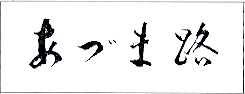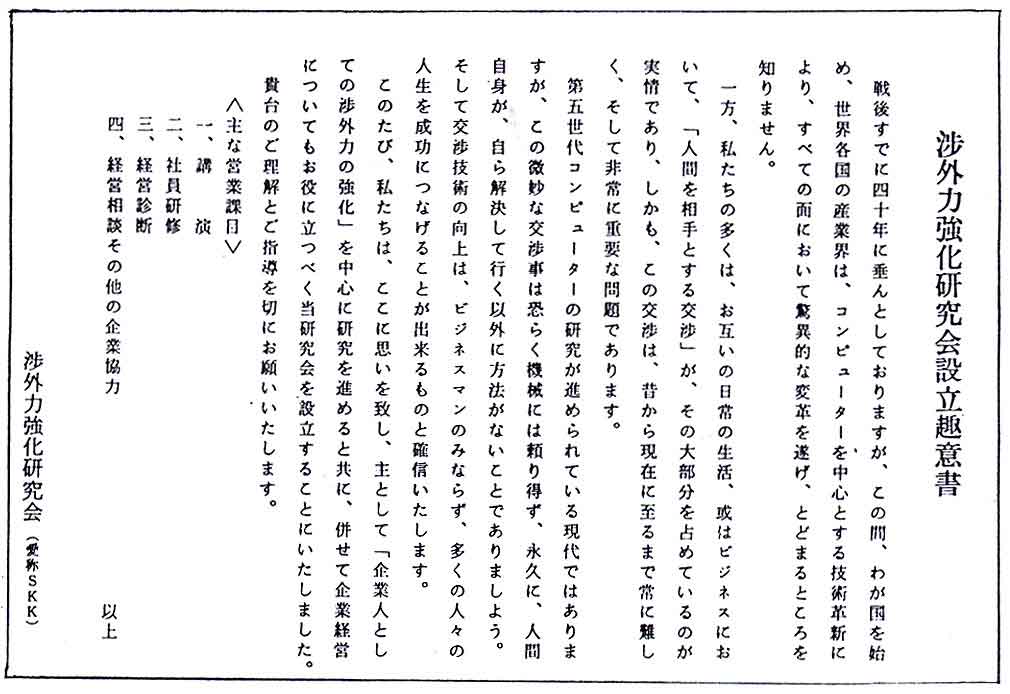国を法によって治める。現代にまでつながる法治国家の理念を最初に確立したのは、聖徳太子である。当時はまだ具体的法(律令)が制定されていなかった。それで、国家のあり方を定める法として定めたのが「憲法17条」である。今から1400年前、推古12年(604)の時と言われている。
国を法によって治める。現代にまでつながる法治国家の理念を最初に確立したのは、聖徳太子である。当時はまだ具体的法(律令)が制定されていなかった。それで、国家のあり方を定める法として定めたのが「憲法17条」である。今から1400年前、推古12年(604)の時と言われている。その第1条の最初の言葉が有名な
『和なるをもって貴しとし、忤(さか)ふること無きを宗とせよ』
「憲法17条」が「和の憲法」と言われるようになったのはこのためである。
当時は、国つ神と天つ神の闘争が猛烈を極めた時代であった。「ヤマト」に「大和」の漢字があてはめられたのは、いつ頃からか?うち続く動乱に疲れ果て、和を切実に求めた民衆の要望から生まれたのであろうか。
太子が「和をもって貴し」と言った背景には、このような長きにわたる動乱の時代があった。それ故に、太子は「仁」ではなく、「和」をもって最大の徳としたのである。
「和」は客観的原理であって、人と人との関係の道徳である。太子は更に上下に和があれば、議論が可能であり、議論が可能であれば「理」が実現される。「理」が実現されれば、事は必ずうまくいくと述べられた。「和をもって貴し」とした太子の言葉はこういう考えの上に立っていた。
だから和の精神は、鎌倉幕府の「貞永式目」に、明治政府の「五箇条の御誓文」に受け継がれた。そして今の言葉で言えば、遺伝子の一部として我々の体内のどこかに残っており、日本社会の基本原理の一角を形成しているのである。
谷沢永一氏がこんなことを言っている。
「日本が世界一長寿国である理由は、冷徹で個人主義でギスギスした生活のアメリカに比べて、和を重んじ、仲間を作っていく生活は心の安定につながり、それが長寿をもたらしているのだ」
7月31日、日産の「フェアレディZ」復活が大きく報道された。日産が名車として世界に誇った「Z」の生産を中止して2年、日産再生のシンボルとしての再登場である。「和があれば議論が、議論が可能であれば道理が生まれ、事はうまくいく」という和の精神は、以外にもこの「Z」復活の原動力となった。
有名なゴーン社長は、社員に対し「Z」に社運をかけると言う事で意識の統一を図り成功した。和の出発点である。その上で日産の名物のように言われていた各部署間の障壁を打ち砕いた。それからは企画、デザイン、技術、販売等といった各セクション同志の夜を徹しての妥協無き議論、こうして一つの筋道が生まれ、名車「Z」が世に送り出された。
何かと言うと、日本的経営はもう時代遅れである、これからはアメリカ式成果主義の時代であるといわれる。しかし、日産の他にも、和の精神によって仲間(チーム)力を発揮し成功した例はいくつも耳にしている。
ソニーがまだ町工場の域を脱していない時代、会社設立の趣意書には「自由闊達ニシテ愉快ナル工場」と記載されていた。そこに躍動しているのは「和」の精神ではないだろうか。
SKK「相互啓発懇話会」は「ことば」の世界である。言葉によってお互いが啓発しあう会である。ことばを尽くすためには「和」がなければならない。「和」があって議論が生まれ、相互に啓発しあうことができる。
こうしてみると、1400年の昔、太子が憲法で諭された『和をもって貴し』とする教えは、意識するとしないに関わらず、日本の至る所で息づいている。
SKKも「和」と「話」を大切に育て、伝統継承の一端を担えたらと思う。
以上