|
「自然」<シゼン>という言葉を、いまほど多く使うことはなかったのではないか。自然保護、自然崇拝、自然科学、自然主義、自然淘汰などなど、探せばキリがない。
「広辞苑」には、
シゼン<自然>=おのずからそうなっているさま。天然のままで人為の加らぬさま。
○人工・人為になったものとしての文化に対し、人力よって変更・形成・規整されることなく、おのずからなる生成・展開によって成りいでた状態。とある。
私は30年勤めた放送局を定年退職した後、東京都の環境学習センターの研究生として、1年3ヶ月研修を受け、自然保護運動に参加いたしました。多摩川の河原の清掃、放置された多摩の杉林の下枝おろし、田植えの助っ人、公園の池のドロ浚い等々。
腰に弁当をぶら下げ、交通費自弁で数年実習をした。65歳を過ぎるあたりから、さすがに体がもたず、都内から湘南に引っ越したのを機会に暇をいただきましたが、肩書だけは残されている。しかし、私の自然保護の信念は捨てがたく、住んでいる市役所が崖の上の樹を伐採などすると、「ワシは東京都の環境学習リーダーだが、訳があり湘南にすんでいる。その樹の伐り方はいかん」などと環境リーダーとしての意見を言い、樹木の大切さを語る‶ウルサ爺〝をやっております。
東京都環境学習センターの実習はきつかったが、地球温暖化による環境破壊も増え、90年後には、東京の下町は海の下になるということも教育されました。
北極、南極の氷山が溶け、ヒマラヤの雪も水となり、海面は1メートルも上がってくる。その分、海は高くなり、下町に海水が流れ込み、街は沈む、という。
そんなことから「自然」という存在に異常に関心が強く、大昔の寒い氷河時代、日本海の海面が下がり、朝鮮半島は九州と地続きになり、暖流が日本海に流れ込まず日本海は大きな湖と化し、日本列島は寒さに震えた。なども聞かされて環境問題の重要性を仕込まれました。そのためか「自然」という言葉の意味にも大きな関心を持つようになりました。
7年位前、この「自然」<シゼン>という読み方に対して、はるか昔は同じ漢字でも別の読み方があり、<ジネン>と発音することも知りました。さらにそのうえに、漢字は同じでも、<シゼン>と読む場合と、<ジネン>と読む場合の字の意味が、それぞれ、まったく違うことを知り、驚きました。
<シゼン>の場合の字句の意味は前に書いた通りですが、<ジネン>の場合の意味はまったく異なるもので、「自ずから然(シカ)る」という意味で、哲学的な不思議な単語だったのです。さらに<ジネン>は<宗教用語>だとも聞きました。
皆様も漢和辞典を開いて目的の字を見つけると、その漢字の下の読み方に「呉」とか、「漢」とかの表示があり、別々の読み方が明記されております。 (小事典には明記なし)
自然 ― ジネン(呉音読み)おもに宗教用語
― シゼン(漢音読み) 普通用語
漢字が日本に入ってきたのは弥生末期の216年、百済の王仁(ワニ)が論語10巻と千字文1巻を応神天皇に献上したのが漢字の日本への最初の渡来とされております。このように調べてみると、日本の弥生時代とは、稲作が初めて中国より九州にはいり、次第に北上しつつある時期で、やっと百済経由で中国製の漢字がはいり、日本でもこれから文字が使われるかといった頃であったのです。
最初に中国から日本に入ってきた時の漢字の読み方は呉音でした。 この発音は呉(ゴ)の地方、および江南地方の発音とされています。ついで入ってきたのが漢音で長安の発音でした。
あの悲惨な前の戦争の時、中国をシナポコペンと呼び、文化の遅れた未開発国としてバカにして戦争を仕掛けたものの、考えればその約2千年前には、日本が未開発国で字もなく、やっと朝鮮半島の百済の仲介で漢字を入れて貰い、「字」のお勉強を始める寸前でした。それに対して、中国での漢字の出現は、なんと紀元前13世紀。遙かな大昔です。大文化国だったのでしょう。
視点を変えます。
私たちはいままで、自然とどのように付き合ってきたのでしょうか。
私たちはいままで、抱いてきた「自然観」を改めて考え直す時ではないでしょうか。
ここまでは「自然」には二つの読み方があり、その読み方がまったく異なる次元の意味であることを知り、おおいに混乱しました。
繰り返しますが、呉音読みの「自然」<ジネン>とは「他者の力を得ないで、それ自体に内在している力によって、そうなること。またはそうであること」という意味であり、実対としての森や川を意味してはおりません。
<ジネン>と読んでいた「自然」に、あえて山川草木などの意味をつけたのは、恐らく明治時代に入り、学校などで国語教育を始める際、日本人が「NATURE」という英語を翻訳する時に「自然」という漢語の字をたまたま思い出し、それを使ってみたら、割合繫がりがよく、ならばと読み方を漢音の<シゼン>に変えてみると、新しい用語として使えることが判ったのではないでしょうか。
(確かな証拠は目下見つかりません)
参考として記しますが、明治の始め、新政府が新しい教育行政を開始するにあたり、用語の検討をはじめました。いままでの昔からの古風単語では、新時代の科学、技術、教育、政治などの学校教育はできないだらう。しからば、新規の用語を作らねばならない。
そんな次第から新用語の開発を始めることになったのでしょう。
かなりの人数の学者がヨーロッパに派遣され、日本に無かった新しい技術用語、社会用語、教育用語を翻訳開発し造語までしたようです。(これは事実です)
帰国してそれらを整理してみると、理科教育用に(NATURE)に当てはまる語だけは翻訳・作成が不可能であったらしい。いまさら「天」「天地」または「山水」では、再び昔に戻ってしまう。
派遣団全員が集合、検討した結果、或る御仁が「しからば‶自然〝を<ジネン>ではなく漢音の<シゼン>という読み方にしたら如何か?」との発言があり、名案なり!とのことで、即座に決まったのではないか。(証拠は無いが、論理性はある)
まさに困った時の神頼みで(自然シゼン)が生まれたのでありましょう。
なお、中国より仏典を通じて取り入れた漢語は、ほぼ呉音読みのまま‶お経〝などの仏教用語に使われ現在まで伝わっているのだそうです。
(藤堂明保 学研・漢和大辞典)
ですから、‶お経〝を聞いても、中国語風?に聞こえ、意味が判らないのは、そのせいなのでしょうが、反面「意味深長」そうな言葉と幽玄なる音調が仏の言葉として、かえって有り難く民の心に染み入ったのかもしれません。
いずれにしても、このあたりの調査は続けてみたいと思っております。
よい参考資料がございましたら、お知らせいただければ幸いです。
|


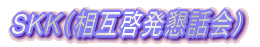
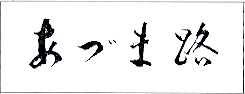
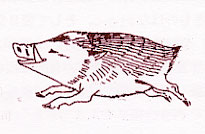

 増産の 除草機を押す」は、当時の私たちを表した名歌だ。
増産の 除草機を押す」は、当時の私たちを表した名歌だ。 ちが水路で野菜を洗ったり洗濯したり、三眠井と言って飲み水とそれぞれ用水は区別されています。畑で働く姿もあり、荷を背負って歩く姿も、たくさん見ました。女性は働き者と聴いていました。
そのとおりです。男性の働く姿はあまり見かけません。数人でゲームをしているところ、たむろしている所など、 子供をおんぶしている男性はよく見かけました
男は遊ぶ事が
ちが水路で野菜を洗ったり洗濯したり、三眠井と言って飲み水とそれぞれ用水は区別されています。畑で働く姿もあり、荷を背負って歩く姿も、たくさん見ました。女性は働き者と聴いていました。
そのとおりです。男性の働く姿はあまり見かけません。数人でゲームをしているところ、たむろしている所など、 子供をおんぶしている男性はよく見かけました
男は遊ぶ事が

 ありました。
ありました。