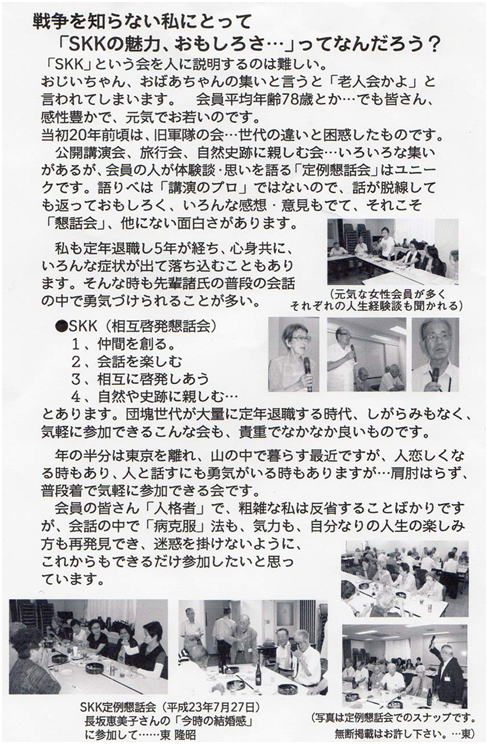|
*
|
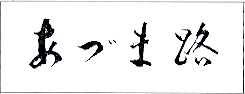 |
 |
65
| あづま路 65号 戦争体験特集 |
平成24年7月 |
|---|---|
| 日本人のすばらしさを見直そう | 栗原 弘 |
| ビルマ戦に参加して | 関口 利夫 |
| 静かなる軍人 | 皆本 義博 |
| 私の大東亜戦争 | 飯倉 豊司 |
| 六年生の夏 | 栗原 弘 |
| 「親父」の記憶 | 東 隆昭 |
| 長かった終戦の日 | 笠原 修 |
| 戦争体験記 | 富樫 利男 |
| 日米秘密情報機関 | 平城 弘通 |
| 戦争体験 短編集 | 会 員 |
| 大木戸句会 | 川和 作二 |
| 夕焼け小焼けの里 | 近藤 美明 |
|
SKK(相互啓発懇話会)は昭和59年に発足以来、東、関口、横山、林、 SKKの主要課題は、日本の歴史、文化、伝統などの研究と普及、および次 この間ボストン美術館の日本芸術の素晴らしさに触れました。日本の素晴ら 今回の「あづま路」は皆本氏の「水上特攻」を受けて、戦時体験特集としま
|
|
戦史などの多くは、師団単位で主として歩兵部隊の活動が中心になっているので、敢えて軍直轄の野戦重砲兵の活動の一部を記して後世に残したい。 私の所属したのは野戦重砲兵第18聯隊だが、この部隊は昭和17年1月のシンガポール攻略作戦から参戦している。シンガポール(当時英国領)は2月13日に陥落し、部隊は3月初めにビルマ(英国領・現ミヤンマー)に転進、ラングーン(現ヤンゴン)― マンダレー街道の進撃作戦(第一次戡定作戦)に参加、ビルマの大半を制した。が、5月24日ビルマ東北部バーモ付近での対支那の戦闘で初代聯隊長を戦死させてしまったことは遺憾千万なことであった。 昭和18年4月部隊は、新しい聯隊長を迎えて、西部のエナンジョンに移動駐留していた。私を含めて同期生3名が赴任したのはその直後である。既に夫々の所属は決まっており、私は第2大隊本部指揮班観測掛を命ぜられた。観測掛というのは、観測班を指揮し、器材を使って各中隊の射撃の諸元(方向、距離など)を決める仕事である。 野戦重砲には2種類(10加・15榴)あるが、わが部隊は10加である。が、途中15榴を配属されたこともあった。10加は下の写真のような砲であるが、1ケ中隊に4門ある。聯隊は2ケ大隊、大隊は2ケ中隊で編成されているので砲は計16門である。兵員はその他の部門も合せて2550名の定員を抱える。(10加とは口径10センチのカノン砲、15榴とは口径15センチの榴弾砲) 昭和19年3月インパール作戦が始まった。わが聯隊は軍命令により33師団(弓兵団)の指揮下に入りインパールの南方からの攻撃に参加した。インパール作戦に加わったのは他に31師団(烈)15師団(祭)でそれぞれ東方、北東方から攻撃した。しかし、制空権は100% 敵に握られた上、4月からは雨季に入り、山腹道は敵航空機に破壊されて兵站線を絶たれてしまったため、わが方は弾薬・食糧・医薬品などの補給が思わしくなく、さらに疫病患者が続出し大変な苦戦を強いられた。これは、攻撃前進にあたって、軍司令官が『1週間でインパールを陥落させる』という言わば無謀な方針を立てたためである。従って各部隊とも弾薬・食糧・燃料・医薬品など1週間分しか携行しなかったのである。いざ始まって見るとそのような簡単な戦いではなかったのである。 しかし、そのような状況下でも、第一線の歩兵部隊は泥水に胸まで浸かりながらインパール市街を望める辺りまで進出して敵と戦闘を繰り返していたのである。
戦をしたり、方向音痴でもあるので一晩中同じ所を這い回ったり、あるいは
敵の前哨線の中に入ってしまって、明け方急いで方向転換したり、よく失敗
をした。陣地偵察で一番いい陣地が見つかって砲を進入させた時は、直後に
敵の集中砲火を浴びたが幸い大した被害もなく、この陣地で敵の要衝の砲撃
に成功した。が、翌朝敵がわが観測所の前方峡谷を隔てた約1000メートル位
の山腹道を列を作って退却して行くのを見た。直ちに射撃に入ったが直ぐに
弾薬が尽き、惜しくも敵の大部隊を逃してしまったことがあった。 暫く膠着状態が続いたが、遂に同年7月15日大本営よりインパール作戦中止の下命あり、やむなく(?)撤退を開始した。 わが聯隊はマンダレーまで後退し集結したが、その頃すでに火砲・兵員とも約半数の損害を出していた。私と一緒に赴任した同期生は二人とも戦死、わが観測班も実勢は3分の1であった。野戦重砲は主として前線の歩兵支援と対砲兵戦・対戦車戦を行っていたが、砲兵部隊でこの有様であるから、第一線の歩兵部隊の労苦、損耗は筆舌に尽くせるものではない。歩ける病人は徒歩で後方にさげられたが、途中で倒れる者が多く、撤退時の街道は至る所に病気で後退した兵の骸が転がっていて幽霊街道と言われていた。 わが聯隊はマンダレーに於いて組織変更をし、大隊編成(すべてが半分になったから)とし、野戦重砲兵第9大隊となった。 改変後も私は大隊本部の観測掛を拝命したが、部隊は休む間もなく31師団の指揮下に入り、追い迫る英印軍をイラワジ河の水際で阻止すべくマンダレー西方地区に展開した(イラワジ会戦)。しかし優勢な空と地上の火力に支援された英印軍は、遂にその下流のニアング方面のわが防御陣を突破し、有力な機甲集団をもって一気にメイクテイラに突入占領した。これによりイラワジ会戦は各戦線とも崩壊した。 わが大隊は直ちにメイクテイラ攻撃に転用され(20年2月末)、その北方地区に展開したが、新陣地では極めて複雑な戦闘となった。砲をメイクテイラ方向に向けていたところ、敵陣地からわが陣地の西方を迂回してわが後方に回った敵戦車が、急にわが陣地を襲って来たのである。急な方向転換が利かない10加では何ともならない。詳細は記述する余裕がないが、敵戦車と刺し違えるような場面もあり、結局砲2門を失うとともに多数の死傷者を出した(メイクテイラ会戦)。 軍は遂にメイクテイラ奪回を断念し、各部隊に後方集結を命じた。わが大隊は残る2門の砲をトングーに移送し、シッタン河を渡河、15師団の指揮下に入り、トングー - ケマピュー道(モチ街道)においてトングー方面よりの敵戦車の進入妨害に任ずることとなった(4月26日)。 砲1門はモチ街道8哩に布陣していたが、5月18日来襲した敵戦車と交戦中、砲の脚部を破損自滅した。残る1門は9哩付近に布陣していたが、これも戦車に襲われ、小隊長以下多数の死傷者を出し砲も破壊された。かくしてわが大隊は砲兵の生命である火砲のすべてを失ったのである。(その後省略)
終戦後、部隊はタイ国に駐留、21年6月日本に帰ったが、部隊と共に生還した者は500名弱であった。
最後の火砲が破壊された時、たまたま私はその場面に直面したので、その詳細を野重18聯隊戦記『砲車の轍』から転記することとする
「最後の火砲の臨終に侍って」 関口利夫 野重9大隊の最後の火砲一門はモチ街道9哩に、対戦車火砲として陣地進入した。われわれはこの一門の火砲にすべてを賭け、恨み重なる敵戦車に一泡ふかせようと、林中隊の志気は旺んなるものがあった。砲の位置は、敵方から東方に伸びる本道がわずかに北に折れる曲り角で、一直線の本道上を狙って道路の左側に脚を開いた。そして近くの林から木の枝を伐って偽装を終わった。砲側から2メートル位離れたところに幾つか防空壕を掘ったが、いずれも水が湧いて水槽のようであった。その日は曇っていたような気がする。 私は大隊本部の観測掛であったが、その日たまたま連絡のために林中隊に赴いたのであった。 「お-いツ 豚だ、豚肉の配給だぞ-ツ」とはずんだ声がする。食糧不足でろくな食事にもありつけない毎日であったので、砲側は歓喜の声で賑やかだった。今は記憶が定かでないが、何時だったか豚肉の配給のあった日に、敵襲か何かでひどい目にあったことを思い出し、一寸ひっかかるものを私は感じたものである。 14時頃、敵の小型飛行機(赤トンボ)が飛来して、火砲の上空をゆっくりと旋回し始めた。偽装した火砲が発見されはしないかと気が気でなかったが、5、6分間ほどで行ってしまった。 それから30分位過ぎた頃である。遥か彼方と思われる敵砲兵陣地から、ゴロゴロゴロ・・・と言う、遠雷の音によく似た発射音が聞こえて来た。 「また前線がやられるな!」と思う間もなく、ヒユ-、ヒユ-と言う弾道音にハッとした。続いて、ダーン、ダーンという地軸を揺がす炸裂音、それが最初からわが陣地周辺に弾着が集中した。ほとんどが至近弾である。 まさか、と思っていたせいもあって身を隠す暇もない。防空壕は水が一杯で入る気もしない。砲側の者はその場に伏せた。 何十発かの砲撃は随分長い時間に思われたが、せいぜい2、3分間であったろう。 静かになった。周囲を見回すと、右前方に伏せていた小隊長の岡田少尉が動かない。右脇腹を抉られて既に息絶えている。腰につけていた手榴弾が炸裂したためであろう。あたら有為の青年が散った。外にも井上清・別部春次伍長らの戦死者と負傷者が何名か出た。 「負傷者は後方へさがれっ」元気な者は直ちに位置について発射準備を整えた。最近の敵の戦法から考えれば、次は戦車が出てくる番である。敵戦車が本道上を来るならば、正に飛んで火に入る夏の虫、いざ眼にもの見せんと、砲側の全員が前方一直線に伸びる本道の彼方に眼を据えた。 カタ、カタ、カタ・・・というキャタピラの音が聞こえてくる。しかし未だ姿は見えない・・・と、急に、ポン、ポン、ポンという迫撃砲の発射音、ヒユル、ヒユル、ヒユルという弾道音、そして、約30メートル前方にピシャン、ピシャン、ピシャンと弾着した。と見るや、真っ白い煙がモク、モクと本道の両側に拡がって行った。「しまった、煙幕だ」前方が全然見えない。
キャタピラの音の大きさは前と余り変らないようだが、近づいて来ることは間違いないだろう。如何にすべきか、と思案する瞬間、煙幕の中からニュッと戦車砲が顔を出した。俄か小隊長の私が指揮をとった。 「射てっ」その一瞬、眼の前で、ダーンという物凄い音がした。と同時に、左右の照準手が「やられたっ」と言って崩れるように跪いた。一人は内股を大きくえぐられ、他の一人は額から真っ赤な血がしたたっていた。 「二人を下げろ」と言ったが、他にも何人か負傷したらしい、どうしたと言う事か・・。 敵方を見ると、敵戦車の砲口が、発射後の砲煙を少しづつ吹き出しながら「どうだ」と言わんばかりにわが方をのぞいている。 わが砲が射った弾丸は何処へ行ったというのか。急いで閉鎖機を開けてみると、何と、発射の形跡がないではないか。こちらが射つ前に敵から射たれてしまったのだ。一瞬の不覚、慌てて龍縄を引っ張った。何か手応えを感じたが、まだ煙幕が残っていて確認できない。第二弾を分隊長と一緒に装填した。すでに砲側の動ける者は分隊長と私のみである。 「射てっ」ダーン・・・。 第二弾の手応えはない。「少し右へ」方向転把を回そうとしたが動かない。敵の第一弾で装置が破壊されたのであろう。ビクともしない。 前方を見ると煙幕が晴れてきた。敵戦車の両側には、すでに歩兵が機関銃を構えてこちらを狙っているように見える。 敵戦車の第二発目が目の前で炸裂した。 「駄目だ、分隊長、ボサにかくれろっ」 分隊長と私は、数メートル左にあるボサの中に跳び込んで身を伏せた。少し離れて私たちの後方にいた林中隊長がとんで来た。 敵の戦車砲は、その後、三分位の間隔でわが火砲をめがけて射ってくる。機関銃は一分位の間隔で、砲の周辺と私たちが潜んでいる草むらをなで斬りするように射ってくる。 何とも手が出せない。このままでいると、火砲は敵戦車に蹂躙されるか、牽引して持って行かれるかも知れない等と不安になって来た。 いつの間にか、戦車の前の路上に鉄条網が張られている。そして射撃は、依然として規則的な間隔で継続されている。 どの位時間が経過したであろうか、あたりが薄暗くなって来た。カタ、カタ、カタ・・とキャタピラの音が静かに聞こえ出した。戦車が少しづつ後退を始めているように見える。鉄条網を張った道路の両側には、それぞれ二、三名の敵兵が、機関銃を構えてこちらを注視している。 鉄条網を張って、戦車が後方へ下がると言うことは、これで敵の今日の攻撃は終り、と言うことなのだ。 砲兵の命、そして今まで、野重9大隊の誰もが、唯一の心の支えと頼んで来た愛する火砲の最後である。 林中隊長と私は、思わず砲に手を合せた。 「不運な火砲よ、ご苦労様でした。申し訳ありませんでした」と、心からのねぎらいと感謝と哀悼の気持を捧げながら・・・。 「せめて秘密部品を持って帰ろう」との中隊長の言葉に、ハッと我に帰った。撃針と照準具を静かに取り外した。 林中隊は、負傷者を収容し、戦死者からは僅かながら遺骨をいただいた上、改めて、火砲に最後のお別れの挙手の礼をして大隊本部の位置へ向かった。私もこれに従った。重い足をひきずりながら・・・・・。 昭和20年5月18日のことであった。 (合掌)
(後記)あの時、仮に二分の一秒でも早く第一弾が発射されたとしたら、もっと納得のいく最後があったのではないか、と思うと残念でならない。
|
|
この春、自衛隊から“1人の軍人”が退官した。在職25年4か月。衆目の一致するところ、その人柄、在職時の数々の功績、手腕からすれば、再就職は大手の会社でも可能であった。実際に、去年末の退職内定時に、早くも各方面から引く手あまたの誘いがかかった。その好意を謝しながらも、彼は謙虚に断りつづけた。
いま、朝8時から夜8時まで勤務のある中小企業で、黙々と働いている。初老の彼に「いまさら苦労の多い中小企業をなぜ選んだのか」と聞いても、微笑を浮かべるのみだった。「静かなる軍人」―とは、彼を知る人々の間でささやかれている言葉である。
× × ×
中学4年のとき、陸軍士官学校を受験したが、身体検査で、肺活量不足を指摘され不合格。しょんぼり帰る彼を、追っかけてきた白衣の軍医大尉が肩をたたいて言った。
「オイ、来年また来いよ。待っているからな」
このとき、人の励ましの言葉のありがたさが胸に深く刻みこまれた。その軍医の一声が、彼を軍人ひと筋の道を歩かせることになった。翌年、陸士に合格、昭和19年7月1日少尉に任官。同年動員され沖縄作戦に出征。その直前故郷に帰り、師事する寺の住職にそれとなく別れのあいさつ。住職は「法名は引き受けた。心置きなく往きなさい」と言葉少なく励ました。
× × ×
沖縄では、特攻隊「海上挺進第3戦隊」の第3中隊長になった。部下30名。海上特攻というのは、長さ5.5m、重さ1トンのベニヤ板製の小舟に、200キロ爆薬をしかけ、自動車エンジンで推進させ、主として敵の駆逐艦、巡洋艦に体当たりして爆沈させることを狙っていた。 彼等の特攻基地は、沖縄慶良間列島の渡嘉敷島で、沖縄本島の首里まで30キロの距離にあった。
20年3月23日から戦闘開始。海上突撃前に敵襲を受けた。たまたま作戦準備の現地指導にきていた大佐が急ぎ本島の軍司令部に帰ることになり、戦隊長から彼の中隊に護衛が下令された。彼はこれを辞退した。第一線を離れ、本島に行くということは、生き残る可能性があった。彼はそれを拒否したのである。曽野綾子が作品「ある神話の背景」で、「軍人のエチケットとは、当時、そういうものであった」と書いている。
上陸してきた敵と烈しい戦闘を続け、部下の約半数を失った。この間島民の集団自決もあった。8月23日武装解除。翌年復員し部下の遺骨を遺族に届けた。
× × ×
生真面目な九州男子の彼は、いつも、沖縄で戦死した部下のことが念頭にあった。書斎に亡き部下たちの氏名をかかげ、朝夕拝んでいた。自衛隊在職中に、いくたびか転任。彼はその都度、靖国神社に参拝し、亡き部下たちに離着任の報告をした。
再就職前に、妻を伴い、沖縄の亡き部下の慰霊に向かった。これは33年間の宿願だった。南部戦跡摩文仁の岩に刻まれた歌「小石もて戦いせしときくにつけ身につまされて悲しかりけり」の前で、彼の妻は、眼頭を拭いていた。身体の弱い妻は「沖縄にはあなただけで出掛けたら・・・」といった。その時優しい夫は珍しく血相を変えた。「沖縄とオレとは切っても切れない。沖縄に眠る部下を慰霊するのはオレの30年越しの宿願だ。妻のお前がなぜ同行できないのか」
× × ×
夫が青春の日をかけて戦った沖縄を訪れた妻は「やはり来てよかった」と思った。那覇からかっての戦場―渡嘉敷島への船の中で、彼は懐かしい郷里に帰るような胸のときめきを感じた。島では村長以下多くの知人が出迎え、午後から慰霊碑「白玉の碑」の前に、全島民が集まって慰霊祭を催した。ことしは終戦33周忌である。彼は村長から祭文を頼まれたが「黙っておまいりしたい」と申し出、玉串をささげ、長く碑前にぬかづいていた。
沖縄の風習に従えば、慰霊祭は33周忌ですべてが終わる。この日の式典が終わったあと、玉井村長は「お国のため亡くなられた人々の慰霊は別だ。村が存続する限り、この慰霊祭は永遠に続けたい」と村民に語りかけ、全員の賛同を得た。その日、夫妻は彼が戦時中世話になった家に招かれた。多くの村民が集まり、夜を徹して飲んだ。戦争を知らぬ若い男女も、島の踊りでもてなしてくれた。翌日の夕方、夫妻は村長はじめ多くの人に見送られ、島を離れた。波止場に並んだ人たちは手を振り続けた。夫妻は島影が消えるまで、デッキに立ちつくしていた。戦後、沖縄をめぐって、「軍民対立」の戦記がつぎつぎに発表されたが、彼のように島民に親しまれた軍人がいたことは、あまり知られていない。 × × ×
3月31日、いよいよ退官の日、彼は制服で靖国神社に昇殿参拝した。沖縄戦での上官、戦友、部下に対し、軍人として最後の申告を終えた彼は、降殿して行く廊下で、急に眼頭が熱くなるのを覚えた。それは軍人としての生涯の終わりのさびしさでなく、ただ「終わりました」という、しみじみとした感懐がこみあげてきたのである。彼が去ってゆく靖国の神苑は、サクラが満開であった。
× × ×
二つある蓑の古きを己着て父と田に出づ雨降る朝を
「これはわたしが尊敬する歌人吉植庄亮氏の歌です。警察予備隊が創設されたとき、この歌のような気持で、先輩のあとに続いた青年のわたしも、いまや老兵となりました。古くなった蓑を他日のために残し、めでたく退官いたします。これからは、自衛隊で培ったものを誇りとし、自衛隊の発展を祈りつつ、頑張ります。ありがとうございました。」これは送別会の席上、彼が述べた謝辞である。 彼とは誰か ― その人の名はいえない。彼の名を書くことが本旨ではないからである。 (昭和52年8月1日 埼玉隊友会・高麗川倫)
|
|
1、中島飛行機製作所へ入所
昭和19年11月半ば、私達は学徒動員令により中島飛行機製作所武蔵工場へ入所した。当時私は中学2年生、学業の途中にあった。
太平洋戦争(当時は大東亜戦争と呼称)は4年目、戦局は敗勢に傾いていたが、国内では誰も戦争に負けるとは思ってもいなかった。その理由は、過去3年間の戦いは殆んど日本軍の勝ち戦さが多かったこと(大本営発表の粉飾か?)と、帝都は敵の爆撃、砲撃を浴びていなかったことによる。
当時の私は、御多分に漏れず軍国少年で、軍艦の名前や、飛行機の型を覚えることに夢中であった。ラジオの臨時ニュースのチャイム、冒頭で流される音楽 ―陸軍発表の時は「敵は幾万ありとても」、海軍発表の時は「軍艦マーチ」が奏でられる― を聞きながら、今日はどこの戦いか、どんな戦果か、と胸をわくわくさせて期待したものであった。 しかし、6月15日の米軍のサイパン島上陸、7月7日の守備隊3万人の玉砕は大ショックであった。報道解説によれば、サイパン島は、日本の本土から2,000キロ、敵B29爆撃機の行動半径内にはいり、ここを失うことは本土(特に首都)の命運を決することになると言う。(政府はそれまで絶対国防圏の要と呼んでいた。)国民は憂慮した。 7月8日、政府は都市の学童を危険から遠ざける「学童疎開」要綱を決定した(8月より実施)。緊急措置である。
さらに8月には ①学徒勤労令(大学、高専の学生と中学上級生が対象) が発令され、9月に実施に移された。
この間に東条内閣は総辞職、7月22日小磯・米内内閣が誕生した。
11月に入り東京都では、それまで中学3年生以上とされた学徒動員を、2年生までに適用することを決定、これにもとづき、私達の中島飛行機工場入所が決まったのである。動員に当り、週5日勤労、1日学業の制度が定められ、毎週1回登校し集合授業を受けることとなった。
この日入所した学校は10校、1000名くらいと記憶している。私達の中学校は2年生1組と2組計100名、服装はカーキ色の制服にゲートル、軍靴(編上靴)、戦闘帽(凄まじい格好だが、都立校の正装である)。
入所式では所長挨拶(工場長)、配属将校(陸軍省より派遣)の挨拶があった。
「大東亜戦争の勝敗は諸氏の双肩にあり、諸氏の一挙手、一投足はレイテ戦(フィリピンでの戦い)に通ずることを忘れるな!」特に天皇陛下の御関心が航空機にあることを述べたことに感銘した。話の中で「畏くも・・・天皇陛下には」と御名が強調されると、その都度(学校教練で教えられたように)私達が、開いた足をザーッと音をさせて締め、踵をつける(不動の姿勢をとる)音が場内に響きわたり、幹部の方々の好感を受けたようであった。
中島飛行機製作所は、東の中島、西の三菱と言われた飛行機の製造工場で、私達の武蔵製作所は戦闘機の発動機を作る工場である。
所在地は南は国鉄中央線三鷹より徒歩20分、北は西武新宿線東伏見より徒歩15分に位置する。工場の広さは全部見たことはないが2万坪位か?東工場(平屋建てで広い)と西工場(鉄筋三階建3棟?)で、国鉄と直結した鉄道が、東西両工場に1本宛引かれ、部品・製品を移送しており、従業員数は不明だが当時としては日本有数の大工場と思われる。
一番驚いたのは、地下通りに中島銀座と呼ばれる売店が並び(一度だけ連れて行かれた)、戦時乍ら日用品が売られていたこと。敷地内には工場、事務所の外に青年学校、食堂、風洞検査室、野球グランド(観客席有)が配置されていた。
私達は翌日から西武線東伏見駅に集合し、隊伍を組んで工場へ通勤した。先ず初期教育は所内青年学校で開始された。講義は主に午前中、工場幹部や帰還将校らの講話、社歌も習った。午後は実技指導、主として部品のヤスリ掛け、鬼工員に怒られた。工具の名前を覚えるのに苦労する。 11月24日昼前警戒警報のサイレンが鳴った。実習中の私達は、指導員の誘導により工場外空地にある防空壕へ入った。壕は泥の平地を掘った素掘り、縦穴式深さ2米、幅1米位(奥は長い)階段状に掘った上に屋根覆いがしてある。底に屈んで指示を待つ。やがて「ずしん」「ずしん」と至近弾(?)の音が地中に響き、30分位経ったら「もう出てよい」とのこと。 後日判明したところによると、来襲敵機は80機、被害者は死者78人(学徒11人)、重軽傷80人、付近住民死者22人。高々度8,000米位からの爆撃のため命中率は低く、工場は少なからず破壊されたが、機能停止には至らなかった。(後日青年学校の講義では、「気流、その他不確実要因が多い中で、あんな高い所からの命中精度が高いことに驚いた」と講師の話。日本軍の爆撃技術と比較してか?と身に応えた。)この爆撃の経験から、今後は警報と共に学徒は工場外に退避させることに決まった。
翌日はB29一機が、戦果確認のためであろう超高々度で来襲した。これに対し、わが方の高射砲が数百発打ったが命中しなかった。
こうしてこの日から、毎月数回敵機の断続攻撃を受けることになる。
12月に入り実習期間を終了し、各職場へ配属された。私は西工場1階、旋盤工場である。旋盤とは、円柱形の鉄材を削って部品を作る仕事である。 2、艦載機の波状攻撃を受ける 昭和20年2月16日(金)は、朝から雨模様の日だった。朝7時のニュースでは、
*(注)機動部隊とは航空母艦を中心に、周囲を戦闘艦が守って航行する組織的艦隊である。この日の航空母艦は2隻であった模様。 そこで私は1人小走りでいつもの道を通り、工場に入った。ところが何時も門際で「お早う。(オス!)」と声をかけてくれる守衛が居ない(何時もは3~4人が両側に立っていた)。人っ子ひとり居ないとはこのことだ。
咄嗟に閃いた。「これは空襲警報が出ているのだ!」と。そういえば、出勤時間帯なのに、さっきの電車の中には人が少なかったことを思い出した。 「危ない!」 私は工場から離れるため、懸命に走った。駅まで走って辺りを見回す。駅前に数軒あるお店も静かだ。いた、いた!同じ組の野村君が人を探している様子。「やあ」と手を挙げると、先方も気付いて、「先生たちがこっちに居るから」と連れて行ってくれた。場所は東伏見高台の崖下横穴防空壕、10人位居た。あとは出勤していないと言う。警報解除まで2時間余。先生からの指示「明日もこんな具合だろうから、空襲警報解除まで出勤しなくてよろしい」全員挙手の敬礼をして別れた。
帰路は西武線被爆のため、学友と線路上を歩いて帰る。線路上を12~3キロも歩いたが、途中爆弾落下点あり10米位の大穴が空き、線路が吹き飛ばされている。今朝通った線路だ。西武線の係員や工夫が作業をしているのを見掛けた。 その夜は灯火管制のため明かりを消して寝る。風呂なし。着衣は上着脱ぎ、ゲートル(巻脚絆)つけたまま。真夜中警戒警報が鳴る。ラジオを点ける。アナウンサー「敵機らしき目標北上あり」との報、B29か、天候調べか、偵察か、防衛陣地探索か、(夜間の発砲は要注意)何事もなく終わる。同時刻、「ずしん、ずしん」と地震のような音と揺れ。ラジオ「敵潜水艦は外房海岸を砲撃しつつあり」と、間もなく、聞こえなくなる。 こうしてその夜は明けた。 翌2月17日(土)は曇り日。朝から敵襲。艦載機だから来るのも早いが去るのも早い。曇り空の上で爆音がするが、自宅付近は被害はない。「今日は出勤しなくてよいのだ」と思うと気が楽になった。殆んど1日ラジオの傍を離れない。父は警防団の召集で不在だ。2月18日(日)も同様にして、1日が暮れる。とても自宅で学習というわけには行かない。
19日空襲警報が解除されたので、家を出て何時も通り西武線東伏見駅下車、隊列を組むと欠勤者が多い。(空襲の多い工場へ出さない親もいるのか?)
友人から私の欠勤した17日の状況を聞く。 この日は警戒警報(準備せよの報)と空襲警報(敵機来襲の報)が、1分の 出勤した後、爆撃跡を見たが、急降下爆撃では屋上→2階→1階と貫通すること。安全だと思われた地下(学友らが避難した所)でも、一部潰れた所があった。2日経過したのに未だ行方不明者を捜索しているとかで、砂利、コンクリート破片を掻き出し、作業を続けている場所を見掛けた。砂利の中から防空頭巾を掘り出した光景も気持ちの良いものではなかった。 午後の休憩時間、友人2~3人と被曝跡を見て回る。たまたま西工場瓦礫跡にヘルメットを被った2人の紳士を発見、よく見ると青年学校(入社教育所)内の写真で覚えた顔=中島知久平大社長が、秘書を連れての被害視察であった。 ご挨拶をした。(雲の上の人である) 「ご苦労さん、1トン爆弾見たかい?」 「いいえ、見たことがありません」 「そこにあるよ」 指差した方向へ行くと爆撃痕の残った柱(西工場ビル)の陰に縦2米、太さ1米位の丸筒型の鉄の塊が横たわっていた。 「信管は抜いてあるから大丈夫だよ」工兵が抜き取ったらしい。恐る恐る爆弾の中へ手を入れると、湿った白いザラザラした砂のようなものに触れる。思い切って片手で掴み出す。臭いを嗅いでみると甘いアルコール飲料のような香りがした。
出した爆薬を外の広い所へ置くと、秘書の方がマッチを近づけたがすぐ火は付かなかった。お二人とはそのまま別れた。多忙な中、僅かな時間でも若者たちと話す。気さくな方であった。 3、空襲の思い出 東京、大阪など大都市や、住宅地に対する空襲は、映像や出版物などで多く語られているが、殆んどが夜間空襲であった。それも人々が寝静まった時刻に来る。恐らく敵方としては①抵抗が少ない。②民間に厭戦気分を起こさせる。等、心理的効果を考えた上でのことであろう。 最初の夜間空襲は昭和19年11月29日、マリアナ方面(サイパン、テニアン等)から出発したB29 20機の洗礼に始まる。 夜中の12時頃、熟睡に入った頃警戒警報が鳴る。音はボーと太く長く鳴る。丁度船が出発する時、港で鳴らす汽笛と同じ音だ。 寝入っていた私達は直ぐラジオのスイッチを入れる。日常の服装に着替える。ラジオからブーブーブーとブザーの音(電話をかけた時の呼出音とも似て聞こえる)、次いでアナウンサーの声「敵、数目標南方洋上を北進しつつあり」―デアル調だ。 *(注)目標とは当時のレーダーで捉えた映像の意味か。 そのまま20~30分待っていると空襲警報、ボーの汽笛が2~3秒宛断続して鳴る。それも、遠くの汽笛、近くの汽笛が交互に鳴るので、急がされている感じがする。 ラジオからはアナウンサーの声、「関東地区、関東地区空襲警報」繰返す。 やがて上空で爆音(エンジンの音)、敵機の爆撃と日本側の高射砲の音20~30分。この日は少数機で、偵察(反応をみる)を兼ねたのか、被害は少なかった。 空襲の正確な記録は少ないが、各種資料(被害を中心に調べた)から拾うと、 昭和19年12月31日~翌1月1日(夜間) 機数不明、浅草方面 昭和20年1月27日(白昼) B29 75機、有楽町、都心 同年2月16日(白昼) 艦載機グラマン、関東地区(先述) 同年2月25日(夜間) B29 130機、東京、皇居内一部 同年3月4日(夜間) B29 150機 同年3月9日~翌10日(夜間) B29 130機、東京江東地区
一番大きかったのは、今でも語り草になっている3月9日~10日にかけての東京大空襲であろう。死者96,000人、罹災者116万人、都庁舎は焼失、政府は焼跡の整理に困惑して囚人141人を募り、刑政憤激挺身隊を結成、錦糸町付近の死体処理に当らせ、3月17日に埋葬を行ったとのことである(東京都100年史)。
更に、昭和20年4月13日~14日(夜間)B29 170機、東京西部、荏原、大森、蒲田 同年5月24~25日(夜間) B29 250機、銀座、新宿、残る区部の大半 わが家は両親と姉と4人(弟妹は疎開中)、中野区大和町、中央線高円寺近くに住居があったが、5月24日夜焼夷弾攻撃を経験した。
焼夷弾は住宅焼尽を目的とするもので、大型弾1発が空中でパッと開き32発にも分散して落下する。 当夜わが家の近く、上空でパツ、パツと開く(高度不明)と、小弾1発 後で耳にしたことであるが、この日中野・高円寺地区の焼死者は39人とのこと、知人もあり、少年時代の辛い記憶である。 序でながらこの日、皇居、丸の内、銀座、霞ヶ関官庁街も大部分火災焼失。しかし、ラジオニュースでは「宮城はご安泰なり」と放送があり、国民は安心した。 3月17日硫黄島守備隊全滅の後、敵の行動半径はもっと近くなり、4月以降は毎日のように爆撃機が襲来するようになった。6月以後は戦闘機も同行、戦爆連合で昼間から来た。戦闘機は「ノースアメリカンP51」で、わが戦闘機「隼」よりやや大きい。6月10日昼B29、300機、P51、70機が東京上空へ飛来、わが方の戦闘機が迎え撃つ。目前でみる空中戦はまるで映画を見るようだ。上下に旋回、後へ回る仕種、はらはら見守る。撃ち合っているのか、音は聞こえないが1分余で白い霧を吹いて墜落したのは小さい戦闘機であった。残念乍ら米機の方が強かった。幸い、わが飛行士は落下傘で助かったようだ。 この日大阪へB29、500機が来襲したことが報ぜられた。被害不明。 6月以降、地方都市への攻撃が多くなって行く。東京へは偵察を兼ねたB29、1~2機が毎日、わが対空砲火も次第に少なくなった。
4、工場淺川山中へ移転 中島飛行機の戦闘機はピーク時には月産2千機を生産したこともあり、国産機の半分は出来ると自負していた。新聞にも工場名はないが、○万機の生産力と書かれたこともある。当武蔵製作所はその中軸部を担っていた為か、真っ先に敵の攻撃の的になったのであろう。 度重なる被爆のため、生産が一部停滞して生産要求に追い付かず、苦心していた。 「交通便利で爆撃に耐えられる工場を!」という目的で、東京淺川(現高尾)の山中に横穴を掘り、機械を持ち込み生産を続けるという計画が、秘密裡に実行された。 私達は旋盤、ミーリング(穴あけ機)等を担当していたが、7月頃移転が発表され、荷作り、発送等を手伝わされた。
引続いて転属発表、「製造部規格部品班」へ行けという。仕事は組立係の注文に応じ必要部品を勘定して在庫から出す(女、子供でも出来る仕事である)。戦時下、製造の流れを把握し、組織を組立て数千人の工員を配置するのは、大変なご苦労だったと思うが、考えてみれば上の方々にとって動員学徒はお手伝いさん程度にしか期待していなかったのである。それでも上司たちは私達学徒を大切にしてくれた。私達自身も、毎日の仕事が特攻隊の飛行機を作る、沖縄戦に直結している部品の管理だという使命感をもって働いた。 朝8:00下り電車が着いて全員揃ったことを確認すると、リーダーの合図で出発する。全員が3列になって歩く。山の方に向かって左側を行進するのだ。染谷さんが先頭に立って、景気付けに「歩兵の本領」(現在メーデーで歌っているのは替え歌)を一節毎に歌う。 大和男子と生まれては 散兵線の花と散れ 染谷さんが一節を歌うと、全員が歩きながら反復して歌う。元気が出る歌だ。2番も3番もあるが、繰り返して歌うと20分位で工場へ着く。 毎日が同じでは?と言う声もあって、「四百余州を挙る十万余騎の敵・・・・」元寇の歌だ。これも良い歌だが歩調が合わないので、次第に歌わなくなった。
工場と言っても、私達の勤務場所は木造の平屋建て。地下工場ではなかった。正面が5~6間、縦長の杉材作りの1階建=小学校の校舎を彷彿させる。真中に通路(1間巾)があり、その両側のスペースを横割りに数部屋に区切った新築だが粗末な作りであった。その中の数区画が、私達規格部品班の勤務場所となった。 仕事は、各工場から注文のあった伝票に基づいて数量を調え、渡す仕事である。責任者(班長)は40代後半の男性、補助者は徴用令招集者と思われる30代の男性、事務員は20代女性2人、そこに私達動員学徒が1班15人位、他の同級生も同様であった。1日の注文、搬出は少なかった。来場者の殆んどは台車であった。 昼前になると昼食を取りに行く。職場毎に2人または4人の当番が組になって山の向こう2キロ以上先の飯場へ行く。高尾山の中腹辺か?この時初めて地下工場を見た。普通の鉄道トンネルと同じ高さ、広さ、機械が唸りを上げて回転する音、チリチリと金属を削る音、トンネル端の通路を通るのに緊張感を覚えたものだ。
昼食は1人当握飯2個、私達が持参した運搬箱(木製、所属名入)が証明である。握飯は武蔵工場の時は米飯であったが、食糧事情が悪化してから高粱が混ぜられ、こちらへ来てからは漸く握れる程度となり、噛むとプツプツと口の中に残った。おかずは沢庵2きれ、これでも家庭の配給より上等であった。 一度幹部(正社員か?)打合せの会合でライスカレーを食べているのを、通路から見掛けた。「軍需工場は贅沢なものだ」と横目で羨ましく通り過ぎたものである。 午後の仕事を済ませた私達は4~5人で裏山へ出かけた。夏の山道は涼しくて気持ちが良い。山襞を尾根まで登る。突如、戦闘機の爆音、上からダ、ダ、ダ、ダと機銃掃射の音。皆地べたへ転がった。P51型機だ。朝から警戒警報が出ていたことに気付く。反転した敵機は獲物を見つけたように急降下。今、私達がいる遥か下方に中央線が走っている。蒸気機関車が長い客車を引いて、一直線にトンネルに走り込もうとしているのだ。煙を吐いて機関車は精一杯走る。「早く逃げろ」と心から祈る。数機の敵機は次々に機銃掃射を終えて去って行った。 その日の午後工場からの帰り道、淺川の駅前通りは負傷者を収容するトラックでごった返していた。客車から動けない人を次々トラックへ運ぶ、重傷か死亡か判らない軍服姿、列車に乗っていた人々は軍人=兵員輸送車だったのだ。乾いた血の色で緑色になったトラックは何台も続いた。この世の地獄だ。帰宅してからラジオを聞いたが、このことに関するニュースはなかった。
その夜は、負傷者か、死亡者を荷台に載せている光景を思い出して寝付きが悪かった。翌日の新聞にも記事は出なかった。 5、終戦 ―玉音放送を聞く― 8月7日、職場に出勤してみると、新聞(タブロイド版ペラ1枚)を前にして、友人、職場の人達が話している。広島に新型爆弾が投下されたという。どんなものか?「原子爆弾」と誰かが言うと、「冗談じゃない!原子の爆弾が破裂したら地球が壊れてしまうじゃないか」と科学に詳しい1人が言う。そんなやりとりがあったが、そのままになった。 外では、昨夜の爆撃で敵が落としていった不発の焼夷弾が見付かって、みんなが騒いでいる。六角形の30センチ位の長さ、学校で教練の時に見たエレクトロン焼夷弾に似ている。「やってみようか」と物理学校のリーダーが工場前の広場へ投げた。パチパチと青い炎が花火のように爆ぜて面白い。火が衰えそうになると水をかける。すると火勢がまた強くなる。「芋でもあるといいのにね」(危険な遊び、空しい遊びだ)。
この頃になると毎晩の空襲なので危険に無神経になっている。仕事も閑になった。友人の南村君が親父の話だが、「この1週間位の間に、何か重大な発表があるらしい」と言う。南村君の父親は厚生省の役人だ。これもこそこそ話で終わって了う。 8月14日夜9時30分ラジオニュースの後に「明日正午天皇陛下の放送があります」と言う。何だろうか、と父に聞くと、「戦局多端な折柄、国民はしっかり使命を果たせ、ということだろうよ」と言う。 翌朝7時頃同級の熊野君が私宅へ訪ねて来た(彼は同じ町内で淺川へ通うようになってから一緒に通勤するようになった)。 「天皇陛下の放送って何だろうね」 「しっかりやれ、ということだよ」 いつも通り高円寺駅から淺川まで、50分位電車に乗る。今日は先生も一緒であった。「天皇陛下の声は聞いたことがないから、皆必ず聞くように」とのご指示があった。 11時40分頃高尾山中の本部前、緑陰に従業員全員が集合する。500~600人位は居ただろうか、思ったより少ない人員であった。中央正面、テーブルの上にラジオが置いてある。 正午の時報、続いてアナウンサーの声「只今から天皇陛下の放送がございます」― 既にお馴染みの和田信賢アナウンサーの声であった。 続いて「朕深く世界の大勢と帝國の現状に鑑み・・・・」天皇陛下のお声、イントネーションが違う。宮中の言葉は京都弁に近いな、と感じた。難しい漢熟語はわからなったが、「・・・米英支蘇・・・その共同宣言を受諾せしめたり」で、戦いを終えると判った。「しっかりやれ」ではなく、「止めたよ」だ。あと君が代が奏せられ、和田アナウンサーの潤んだ声が続き、降伏を確認したのである。
放送終了後、工場責任者(工場長ではない)からの伝達があった。
「これで戦争は終わりましたが、それぞれ残した仕事があると思いますので、所属長の指示に従ってください・・・・・」「女子の方は東京を離れて田舎へお帰りになることをすすめます」と付け加えた。降伏したからアメリカ兵が占領に来るのだ。
職場へ戻った。ほっとしたという気持ちは全くなかった。チームリーダーの染谷さんがお世話になった部署へ精算や連絡があるからと、私と平出君に一緒に来いと言う。職場の小屋から小走りに山道を走った。8月の空は真っ青、白い雲が浮かんでいた。
「仇討ちは出来ないのかな」と私が言う。平出君は「警察官を増やして力を温存しないとな」染谷さんがそれを聞いて「もちろん、約束した条件が違えばまた立ちあがる準備を、しておかなくてはいけないよ」誰も降伏の後に来るものは判らなかった。
職場へ帰ると皆がガヤガヤ話している。工場の大人も居る。
1)支那大陸で日本軍がやってきたこと。
2)東欧でドイツに占領され、ソ連に再占領された国は、15歳以上の 話は何時までも続く。「母や姉妹がやられてなるものか!」「特攻の若者、玉砕の兵士たちは、この辱めを受けないため、家族のために命を捧げたのではないか」涙が出た。
(注) 後世、平和が来てホッとしたと多くの人が語っているが、私達には
占領軍が来る恐怖の方が強かった。 その晩はよく眠れなかった。横になると溜息。父は「赤穂義士を見習って、何十年経っても仇を討たなければ・・・・」と言う。
明くる日から3日間、用事はないが淺川工場へ通った。工場へ通ずる道の角々には保安のため、腕章を付けた歩哨兵が立った。街中には降伏に反対する将校たちの宣伝ビラが撒かれた。飛行機からも撒いた。ガリ版刷りで「敵は、畏くも天皇陛下を沖縄へ移さんとしている。我ら絶対許さず!」と。 3日程工場へ出て、8月20日から学校へ復帰した。私達3年1組は20人足らず(最も減員が多かった)。他の工場へ動員された者も統合し、これまでの5組が3組に再編成された。 朝礼で校長先生の言葉「戦争には敗れたが、わが神州は不滅である」この言葉が少年の脳裏に焼きついて離れなかった。 (終) |
|
太平洋、鹿島灘からアメリカ軍が上陸すると言うので、学校の校舎に兵隊さんが常駐するようになった。本土決戦である。運動場は開墾して、イモ苗が植えられていた。主食が「サツマイモ」に変わってきた。茨城一号は大きくなるが味はまずかった。薄く輪切りにして、粉にしてダンゴにして食べたると、おいしかった。 我が家の隠居家に兵隊さんが住み込んだ。近所でも、空き家、隠居家は兵隊が常駐した江東集落に軍の本部があった。宇都宮出身者の多いこの部隊で、余興の「八木節」を聞かせてくれたり、楽しかった。兵隊たちは赤いご飯を食べていた。コーリャン飯だ。 1億火の玉となって、大本営のラジオ放送は必死の形相になってくる。鉄類の供出、金目の物はすべて供出するようにお触れが出る。愛国心に逆らう、国に協力しない人は「非国民」と呼ばれて、まわり中から罵倒された。 小学校で松根油の話が出て「松脂」を集め供出するよう呼びかけがあった。これで飛行機の燃料を作るという。手后神社の奥の山林に松の木を見つけては、鋸で傷つけ、竹筒の中に集まるように仕込んで帰る。翌日は脂が一杯たまっている。学校に持って行った。本当に役立ったんだろうか? こんもりと繁った杉林の裏山と母屋の間に裏庭があった。木犀の植え込みがあって良い香りを漂わせたりしていた。甘柿の木があってよく登って柿を食べたものだった。その甘柿の木の下に防空豪が掘ってあった。
昭和17年に長兄は近衛師団に、昭和19年に次兄は宇都宮の42部隊と兵隊に行って留守、また三兄は16歳で国鉄に勤めていた。我が家には4番目の兄14歳を頭に五人の兄弟姉妹が住んでいた。多分、父が掘って作ったのだと思うが、隠居屋の裏に、縦穴で意外に大きな防空豪があった。材木で上から梁を渡し、藁や茅を積んで上から土をかぶせた。中は大きく家中の者が入れた。むしろを敷いて、食べ物や非常用のものが保存されてあり、中で遊んだりした。じめじめと湿気が多かったのを覚えている。その防空豪は一度だけ使った。昭和20年8月3日、水戸の空襲の時である。 7月も末に入ると、空母を含む敵機動艦隊が鹿島灘沖に常駐するようになり、 艦載機の攻撃が多くなってきた。P51やグラマンは我が物顔に飛行場(水戸通信学校)を攻撃した。日本の飛行機の反撃はない。ここの飛行場は無線用の高等練習機が多かったが、家の近くまで飛行機隠蔽用の退避壕を作ってあり、連絡用の誘導路が引かれた。その飛行機も遠慮なく艦載機の攻撃を受け、民家の火災事故も起きたりした。 8月1日 早朝、明けやらぬ暗闇に稲光がする。雷のような轟音と共に砲弾が上空を飛んでいく。はるか後方で大きな爆発音が聞こえる。大洗沖の敵艦船から勝田の日立製作所水戸工場への艦砲射撃である。30分も続いたろうか、生きた心地がしない一夜を過ごした。翌日、近くの谷田部落辺りの田圃に
4,5㍍の大きな穴がすり鉢状にあいている。砲弾の落下地点だ。破片が飛んで、当たったら木も倒れるという。 8月3日夜 空襲警報が発令されると同時に 爆撃機B29の編隊が独特の爆音をたてて飛来した。一発の爆弾から 32個の焼夷弾が飛び散り、花火を見るように、ぱらぱらと散らばって落ちる。やがて水戸市街方面が夕焼けのように赤く染まり、B29が何機も何機も、ピンクに下腹を染めて、ゆったりと水戸市街に向かうのが見える。 自宅は4km程離れているので全く心配はないと思っていたが、焼夷弾の投下が大分近づいて来るように思えて、緊張を覚えながら、防空壕の中で夜を過ごした。
空爆は酒門小学校あたりまでで、我が家の石川地区は全く心配なかった。
六角形をした60センチ位の筒状の焼夷弾は町付部落辺りの畠に、スポンスポンと埋まり込むようにして入っている。 不発弾が多い。生ゴム状の油が詰まっている。これで遊び用のゴムボールが作れる。同級生の川上君の兄貴は一級上だったが、不発弾の雷管をいじっていて爆発し、内臓破裂で死亡した話がクラス中で話題になった。 高等科の生徒は軍需工場。初等科の我々は裸足で学校に行くが、勉強はなく、運動場で畑仕事をさせられた。運動場にはサツマイモが植えられた。 水戸から大洗に通ずる水濱街道(八間道路)の両サイドは砂利の多い土地で、我々小学生はそこを開墾して大豆を植えて、手入れをしていた。
そこにアメリカの艦載機 「グラマン」が低空飛行で一斉射撃を浴びせる。轟音が頭上を飛び、「伏せて!」女性教師のヒステリックな声が耳をつく。 艦載機の我が物顔な攻撃は民家にも及んで、夜光弾のためにわら屋根に火がつき、火事になったりした。 8月6日広島に新型爆弾が投下された。ピカドンで広島は草も生えない廃土となった。続いて9日に長崎にこの原子爆弾は投下された。非戦闘員も区別のない地獄と化したのである。大勢の人が亡くなった。 8月15日 珍しく、P51やグラマン(艦載機)は一機も飛んでこない。お昼に玉音放送があるという。暑い日で、裸足で畑から帰り、隣家のラジオを大人や兵隊達と一緒に聞いた。雑音が多くて良く解らない。 「忍び難きを忍び」というのを覚えている。 「負けたんだ」大人達がつぶやいている。ポツダム宣言の受諾を天皇陛下が決めたのである。 戦争が終わってホッとした気分もあった。これからどうなるか全く解らない。 |
|
終戦の時、私は旧制札幌一中の二年生でした。憧れの中学に入ったものの、北海道とはいえ風雲急を告げる戦時下、勉強どころではなく、終戦の年度の年に至っては初めから勤労動員に狩り出されました。 我々のクラスは、札幌近郊の簾舞地区の農家に2,3人ずつ分宿、暗渠排水や田の草取りなど、結構腹の空く重労働の日々でした。担任の宮崎先生(綽名はリック)は生徒の働きぶりをみて“一中生裸になりて田の中で米増産の除草機を押す”と吟じた光景でした。必勝を信じ、銃後の守りにどんな苦労にも耐える軍国中学生の時代だったのです。 その頃、何時も朝食後脚絆を巻き、同宿の友人と朝刊を読み語るのが唯一の楽しみでした。広島に次いで長崎にも新型爆弾が投下され、想定外の被害に“これは国際法に違反した重大な人権蹂躙だ”と社説を読んで、凄い不安と憤りを覚えた記憶が鮮明に蘇ってきます。 終戦の日8月15日は朝から真夏の太陽がジリジリと照りつけていました。 午前中、仕事の合間に小高い丘から直下の川向こうに建つ国立結核療養所を眺めていると、鐘楼の音を合図に今日も木炭を焚いた霊柩車が数台。野辺の送りの悲しい行列です。戦争の役にもたたず、ただ空しく散った若者に想いを馳せ、人生の無常を痛感しながら、しばし黙祷をささげました。その時代、沢山の有為な若い人材が結核に罹り、為すすべもなく人知れず世を逝った事は国家として、悔やまれる実に悲惨な出来事だったのです。 15日は丁度お盆の中日で、交代で墓参などの為に里帰りが許されていました。居残った我々半数近くは、前以って通知のあったその日の正午に簾舞国民学校の校庭に集められました。リック先生が、どこからか借りたのだろう携帯ラジオを持参“只今から天皇の玉音を通じて、重大な発表がある”と突然告げました。直立不動で聞き入りましたが、電波が極めて悪く、緊張のせいもあって内容は全く理解できません。リック先生の解説で“日本はポツダム宣言を受諾し、ここに大戦が終わった”と玉音の内容を説明してくれました。我々は皆頭が真っ白になり、戦争がこんなにも呆気なく終わるものか?と信じ難い思いでした。
先生の指示に従い取り敢えず帰宅することになり、荷物を纏めての帰途、大空を眺めると入道雲の合間にB29が一機南に向かって悠々と飛び去るのが恨めしく、あれから半世紀以上経っている今日でも、空を眺める度に想いだされます。
夕方家に帰り着くと、母が青ざめて、“木伏さんの小母さん(父の従妹)が今朝、勤労動員で丘珠の飛行場の防空壕建設中、落盤事故に合い数名の人達と生き埋めになり、そのまま帰らぬ人になった“と言う。この小母は前年(昭和19年秋)ハルマヘラ島で戦死した小生の父の内報以来、毎日のように我が家を訪ね、母を慰めてくれた掛け替えのない人でした。悲嘆にくれる母に付き添って、木伏家の通夜に参列、終戦の日だけにその不遇に悔しいやるせなさに涙しました。こんなアクシデントがあったせいか、終戦のショックよりも身内の思わぬ不幸が脳裏に焼きついて、生涯忘れられない日になってしまったのです。
通夜の帰り道、その日から灯火管制の緊張から開放された家並みの灯が散見され、昨夜までの暗闇と打って変った異様な雰囲気に、戦争が終わった事が実感されました。これから一体どんな世の中になるのかという不安と、長い間の緊張から開放された安堵の気持ちが交錯して、母の手を握らずにはいられませんでした。 そんな想いは時の流れに色褪せる事無く、70年近く経った今日でも、その感慨は深く脳裏に焼きついています。 完 |
| 1. 陸軍航空士官学校卒業と北朝鮮への赴任 昭和17年4月、私は新潟県立村上中学校4年終了後陸軍予科士官学校に入学した。その4ケ月前の昭和16年12月8日にわが国は米英に宣戦布告して太平洋戦争に突入した。この時点では既に陸士の入学試験は終了しており、成績上位者に行われる憲兵による家庭調査も済んでいたので、軍国少年であった私はこの宣戦布告を知って、これで難関と言われた陸士の入試に私が合格するのは決定的だと勝手に決めて喜んだ。 昭和18年10月、入学して1年半経過後、私等の兵科が決定された。 総数2千4百名の丁度半分の1千2百名が歩兵、戦車兵等の地上兵科として陸軍士官学校に、残りの半分の1千2百名を航空兵科として陸軍航空士官学校に入学を命ぜられた。 従来の地上兵科の人数を大幅に削減し、航空兵科の人数を大幅に増加した決断であった。太平洋戦争は大洋に囲まれた島々の戦争であり、戦争の勝敗は、陸軍よりも海軍の、海軍よりも空軍の実力が左右する。空軍力は、技術力と経済力がベースであり、日本はこの点で次第に米国に押されていった。 昭和18年に入ると、日本軍は太平洋の各所で制空権を米軍に奪取され、この事により輸送船等の航行が困難となり、戦局は急速に傾き、昭和20年3月の陸航士卒業時はわが国の敗色は決定的となった。私等は卒業式の翌日、任地の北朝鮮に向けて東京を発った。 私等は北朝鮮の東海岸にあった陸軍の連浦飛行場の第11教育飛行隊に赴任し、優秀な操縦の熟練者から連日飛行訓練を受けた。 当時の北朝鮮は日本の領土であり、日本の内地とは違って米軍の爆撃も無く、飛行演習には好都合であった。7月1日には陸軍少尉に任官、沖縄の米軍上陸等による重大な戦局から、私等は近い中に特攻隊に任命される見通しであった。 2, 生き残ったのは僅かな運命の差 67年前に終わった大戦では、極めて多数の方々が亡くなった。太平洋戦争の南方諸島における戦争は、空軍力によって勝敗が決まった。米軍に制空権を奪取された後は、日本軍は為す術がなく、海軍と、陸・海の航空部門は壊滅的な損害を受けた。中国のような大陸の戦争とは著しく性質が異なるものであった。 私達陸士58期生の同期に相当するのが、海軍では海兵73期生である。彼等は海軍の損耗が激しかった為に、学業が大幅に短縮され私等より1年早く卒業して実戦に参加したので、戦死者は全員の3分の1に達した。 大戦の末期には、もはや日本軍の劣勢を覆す術は特攻以外には無くなり、多数の若い飛行士が空に散った。私の場合、北朝鮮に於ける飛行訓練はこの特攻の要員になることを意味していたが、飛行技術の未熟と飛行機の不足によって特攻に参加するに至らなかった。陸士の1年先輩の飛行士は、海兵73期並の戦死者に達した。 このような生と死の境は、将に天運としか言いようがなく、私が生き残ったのは僅かな運命の差に過ぎない。 3,旧ソ連抑留へ 北朝鮮で行動を共にした約百名の年令約20才の同期生は、終戦の命令を受けた後は、気持ちの整理とその後の事を考え、大いに悩んだ。 私等は、軍司令官より、北緯38度線以北の北鮮地区は、間もなく進駐して来るソ連軍に武装解除を受けるように待機することを命ぜられた。然し、過去の戦争の歴史によれば、戦勝国は戦敗国の軍の指導者(現役の将校全員を含む)の生存を赦さず、死刑にしたという事実を知っている。 私等同期生は互いに額を集めて今後如何に行動すべきかを協議した。その結果、武器をトラックに積んで逃亡し、ゲリラになって戦う事を考えた。 然しながら、当時満20才頃の私等同期生のこの物騒な企ては、軍司令部からの通達と部隊長からの重ねての指示によって終りを告げた。ソ連側は武装解除後は将兵を確実に内地に帰還させること、将校には軍刀と拳銃の所持を認めることを確約したから、絶対に部隊を離れたり、秩序を乱すような行動を慎むようにとの指示であった。 このようにして、九月に入り、ソ連軍が進駐し、武装解除は事なく終了した。この当時は、日本軍の誰しもが日本に帰還する事を信じて疑わなかったのである。 スターリンは、日本人軍人のソ連抑留はポツダム宣言の主旨にもとずき、終戦当時は考えていなかった事が現在では知られている。 旧ソ連は日本との条約を一方的に破棄の上、終戦の直前にソ満国境、樺太及び千島に進攻したが、この機会に、日本の北海道の北半分の地区を実力で占領しようとした。然し、この火事場泥棒的野望は不成功に終わった。その原因は、樺太、千島の日本軍が終戦前に善戦してソ連軍の南下の速度を遅らせた事、そしてソ連のこの野望を米国の大統領が知って明確に拒否した事によるのであった。 スターリンは、この野望の挫折に激怒し、急遽日本軍人50万人を強制抑留する指令を出した。ソ連抑留の決定の原因については、過去に色々と言及されたが、これが現在では正当なものとされている。 エラブカの収容所は将校用であり、国際法により将校への強制労働は禁止されていたが、ソ連側は日本人が生活する為に必要な労働は強制労働ではないと主張し、可成りの広い範囲の労働を私達に強制した。即ち、燃料用の木材の運搬や伐採、食料確保のための農耕作業、収容所内の各作業の他に波止場における荷役作業等を強制した。 将校収容所とは言っても衣食住の条件は極めて悪かった。私等若手の者はほぼ連日労働に従事したが、食料不足で常時空腹状態であり、抑留生活は苦しいものだった。 旧ソ連抑留は、国際法を無視した旧ソ連の暴挙である。絶悪な生活条件と苛酷な強制労働により、抑留された日本軍人総数約55万人の10%に達する約5万5千人が、抑留中に死亡した。 日本政府の努力に拘らず、死亡者の遺骨収集は僅かに約30%に達したに過ぎず、約70%に相当するご遺体は、現在もなお主としてシベリヤに残されており、遺骨収集の目途は立っていな 3,戦争体験から得たもの 上記のように私の戦争体験は太平洋戦争に入って以後の比較的短期間であるが、戦局悪化により特攻隊予備軍として北朝鮮の地で教育され、死を覚悟した毎日であった。 陸士の一年上の先輩方、海軍兵学校の同期に相当する同年輩の方々の多数が、特攻で散って行かれた事を決して忘れる事は出来ない。 上記のように私の戦争体験は太平洋戦争に入って以後の比較的短期間であるが、戦局悪化により特攻隊予備軍として北朝鮮の地で教育され、死を覚悟した毎日であった。 陸士の一年上の先輩方、海軍兵学校の同期に相当する同年輩の方々の多数が、特攻で散って行かれた事を決して忘れる事は出来ない。 旧ソ連抑留は戦争に関連した体験だが、その生活の苛酷さは忘れ得ない。 人間の一生は、平和な時代でも一般に言って苦難は付きものである。 ソ連から復員して後、幸いにも大学に進学でき、戦争とは無縁の平和な時代に、民間人として働いてきた私は、各種の人間社会の苦難と遭遇した。元来田舎者の世間知らずで短気な性格で、平和な時代の人間社会の苦難には弱く、挫けそうになる事が多かった。このような私を支えたものに上記の戦争体験による思いがある。 86才になった現在も健康で、仕事と戦没者の慰霊等僅か乍ら社会奉仕も出来る事は、そのお蔭であると思う。 以上 |
|
警察予備隊入隊 ここまで述べてきたように、敗戦後、世の中は目まぐるしく変っていった。 占領軍の軍政のもとで、いわゆる「戦犯」を裁く東京裁判が行われ、東条英機元首相以下七人が絞首刑となった。マスコミは、占領軍の規制下で旧軍の責任を追及し、労働組合のストを扇動したりしていた。 それは戦場経験者にしかわからない勘であった。 (・・・・・・中略・・・・・・) マッカーサー元帥は、国連軍部隊を仁川に上陸させ、北朝鮮軍の背後を急襲したため、南下していた北朝鮮軍部隊は敗走につぐ敗走を重ねた。こうして朝鮮半島の統一がなるかと思われたとき、中国共産党の大軍が鴨緑江の国境を越えて北朝鮮軍を救援し、北緯三八度線まで押し返すに至ったのである。 以上のような朝鮮半島情勢の緊迫から、占領米軍の大半が朝鮮に出兵し、それに伴い、日本国内の治安状況はますます悪化の兆しを見せていた。 これに対し、昭和二五年七月八日、マッカーサーは吉田茂首相に対し書簡を送り、早急に警察予備隊七万五000人の設置と海上保安庁の八000人増員を命令していた。 日本政府は直ちにこれに呼応して、警察庁を主管として募集を行ったが、なんと七万五000人に対し三十万人以上、たしか三五万~三六万人の応募者があった。 昭和二六年六月には、陸士五三期の堤彦男さんが応募して入隊したと知った。私も、「この警察予備隊は、将来の日本国防軍になる」と予感し、入隊したいと思った。 ところが、妻はもとより、陸士入学のときあれほど喜んだ壱岐本家の人々も大反対なのだ。現在、よい職業についていながら、何で税金泥棒といわれている警察予備隊に入るのか、という理由だけで・・・。 募集条件の待遇は、旧陸軍大尉は一等警察士として採用し、月俸一万六000円を給すとある。広島伸鉄では二万五000円の給料だから、約一万円下がるわけだ。経済的にも承服しがたい、といわれるのも無理はない。 しかし、私は戦場の生き残りであり、戦死した連中に対する責任がある。否応なしに日本という国を守るために死んでいった連中である。 私は支那戦線にいたから、割と苦しい思いはしたけれど、たとえばレイテ、サイパン、テニアン、硫黄島、あるいは沖縄ほどの悲惨な戦闘は経験していない。だが、そういうところに行った連中がどんな死に方をしたかということについては関心があった。 そういって、やっと皆を説得することができた。 かくして昭和二六年十二月五日、私は、神奈川県横須賀市久里浜の警察予備隊総隊学校の幹部学生として入隊することになったのである。 (注)総隊学校の就学期間は二ヵ月 警察予備隊総隊学校 警察予備隊総隊は、警察予備隊創設当時から、幹部の養成学校として横須賀市郊外の久里浜町に置かれていた。旧日本海軍の施設で、戦後は米軍が接収して使用していたらしい。 私たちが収容されたところは、十六畳部屋に鉄製の二段ベッドがぎっしりと詰まっていた。そこの一つのベッドの下段に私が荷物を置いたときに、既に上段にいた男が、「僕は陸士五五期の本坂洋という者です」と挨拶した。 「僕も五五期の平城です」と挨拶を返したが・・・・ (・・・・・・ 中略 ・・・・・・) 学校では、米軍式の教練。不動の姿勢は旧軍と同じだが、左向け左、右向け右、回れ右などは旧軍と違い、一挙動遅れて、カチッと 教練では、弾薬を豊富に使った射撃網下の匍匐前進訓練を、妙に深刻に憶えている。地上五0センチくらいのところに鉄条網を縦横に網の目状に張り、その下を匍匐前進していくと、三0メートルくらい先の横合いから頭上に機関銃の実弾をダダーと浴びせかけられる。 旧軍では、弾薬欠乏のせいなのか、こんな戦場体験訓練はやったことがなかった。弾の下を潜ってこそ一人前の兵隊になれるというのが旧陸軍の伝統であったが、これは実際に戦場に立たないと味わうことができない。それが、米軍式では、戦場に立つ前にそれを体験させ、しかも無造作に多量の弾薬を使用するのだ。 私たちは慣れているけれども、戦場経験のない連中は、みんなびっくりしていた。旧軍では、補充兵が来ても戦場でまた実戦教育をし直さねばならなかったが、米軍は実戦的な状況下で訓練するので、補充兵は短期間でどんどん戦場へ出せるわけだと合点した。 学科も警察予備隊の誕生の所以や使命、組織、将来の動向など興味のあるものだった。 私たちは約四0名単位で一区隊、計五区隊編成の学生隊で、学生隊長は警察出身の加納二等警察正(自衛隊の二佐相当)、区隊長は島根県のある村の村長をやってから志願して入ってきた山崎顕三等警察正(自衛隊の三佐相当)だった。山崎区隊長は村長経験者らしく、私たちの面倒をよく見てくれた。 (・・・・・・中略・・・・・・) ・・・・このときの区隊の学生は、主として陸士五四期から五七期生、および海兵六八期から七二期までの追放解除組であった。 この後、保安隊、自衛隊となるのだが、この山崎区隊長の徳を慕って、区隊会がしばらく催された。その発起人、幹事はたいてい私が引き受けた。山崎区隊長が病気で逝去される二年前、私はすでに退官していたが、五七期の皆本義博君とともに幹事を務めたのが、山崎区隊会の最後となった。 (・・・・・・以下略・・・・・・) |
|
落合 登美雄 終戦を迎える6ヶ月位前に、少年航空隊に志願するよう命ぜられ試験を受けさせられた。甲種合格となる。若し戦争が長引いていたら少年航空兵として戦争に駆り出され、今この世に居なかったと思う。戦争が早く終わってよかったが、戦争程野蛮で悲惨なものはないだろう。戦時中は食糧難で、配給制度で食べ物に困ったものです。幸い私は広島県の中国山脈頂上に近い片田舎に育ったので、生活に苦しい中でも、割合食べ物はあった方でしょう。唯子供心に、「お八つ」は干したバナナや、母親が御飯を釜で炊くので「おこげ」を御握りにして食べたのを憶えています。戦争自体は経験していませんが、どんなことがあっても戦争はしてはなりません。世界が平和で、豊かで明るく暮らせることを祈ります。 終りになりましたが、小生が理事長職在任中は、会員の皆様には大変お世話になり、ご協力賜ったことに心から感謝いたしております。 三木 忠 (昭和9年9月生まれ) 戦争が激しくなった昭和19年9月17日、大阪天王寺師範付属国民学校4年生の私達は、親元を離れ大阪府南河内郡の金剛山の麓の集団疎開地へ向かった。昭和20年3月13日の深夜に全員叩き起こされ、大阪市街地方面の空が真っ赤に染まっているのを見た。大阪大空襲である。先生は大阪は全滅かも知れないと仰る。私の家は無事であったが、多くの友人の家が焼かれた。 依田 武敏 昭和20年3月10日の東京大空襲の時は国民学校4年生で、板橋区に住んでいて空が真赤になるのを見た。5年生新学期には学校が閉鎖になり縁故か、学童疎開かと云われ、群馬の水上に集団疎開をした。水上は未だ雪の中の世界だった。終戦後9月早々には東京の家に帰った。わずか半年のことだったが、食べる物のないつらい体験だった。全然無い訳ではないが飢餓状態となり、口に入るものはなんでも口にした。絵の具までなめてしまった。3~4ヶ月で栄養失調になった。道端の野草でも、毒ではないものは何でも川で洗っただけで口にした。 この体験は、それまで肉、魚は一切口にしなかった私にとって、貴重なものだった。お陰様でこれ以後食べる物は何でもおいしく戴けるようになった。一人の生活になって10年、自分でバランスさえ考えれば、バランスのとれた食生活が送れ、毎年健康診断を受ける費用以外、お医者さんに払う費用は零という生活が送れている。寝ることと運動すること、そしてこの食生活を維持することで快適な生活を送っている。 布野 公子 昨年末長坂様のご紹介で入会させて頂きました。これからは皆様から色々勉強させて頂けることを楽しみにしております。 さて戦争体験の件ですが、私事小学生で京都の東山区に住んでいました。幸い京都には恐ろしいB29の爆撃もなく、又父がクリニックをいとなんで居りまして、患者さんに山科の、農家の方も多く、いつもお米、玉子、野菜、トリ肉etc.届けて頂き、喰べ物にも困らず、父も戦争にいかずということで、まことに申し訳なく思っています。 伊藤 啓子 私の場合、戦争中の体験がなかなかつらくて文章に書くのはむつかしいと思い、失礼させて頂こうと思いましたが、80才よりはじめました俳句に、たまたま該当する句が少しありましたので、拾って書き出しました。 両親、長兄が病死、三人の兄出征し二人が戦死、一時は姉(18)、妹(11)の三人のみが、暮らしていたときもありました(私は現在86才です)。 家族写真に子供六人昭和の日 遠き日の姉妹で焚きし門火かな 敗戦忌わが青春は鍬と鎌 黒髪の豊かな二十歳終戦日 父母兄弟知らぬ世を生き墓洗う 花吹雪あと幾たびの九段坂 啓子 小田 正二 私は昭和7年12月8日生まれですので、太平洋戦争終戦の昭和20年8月15日は旧制中学1年生で、12歳のときでした。4月入学の早々、軍人勅諭に則った教練を受け、銃剣を持って教育されました。軍国主義教育を徹底的に受けました。そして幼年学校を目指して特訓の毎日でした。お国のために生命を捧げることには何の抵抗もありませんでした。しかし、その目標も終戦で白紙となり、失ってしまいました。
教科書は半紙に印刷された粗末なものでした。教育方針が未整理なこともありまして、ところどころ墨でGHQの指令のもと抹消されたものでした。そのような状況下ですので精神的な混乱はいたるところで感じられました。しかしまもなく国民主権の民主主義体制が全般的に確立されて大きな夢と希望が湧いてきました。
私は新潟県の県北、村上町の県立村上中学校生でしたが、家が農家でしたので、幸い食料面では都会のような飢餓状態ではありませんでした。2年後には、学制改革により新制高校に移行され、女子生徒が入学して共学となり、疎開してきたもの、予科練や外地から再び戻って再編入してきたものなど、種々雑多な状態でした。しかし混乱の中にあっても絶えず未来に明るい光が輝いておりました。
2011年昨年は戦後70周年を迎え、太平洋戦争の悲惨な状況の特集などで改めて認識させられました。今日のこんな豊かな日本の中で皆が幸せに生活しておられるのは、あの戦争の大きな犠牲の上に築かれたものであることは言うまでもありませんし、私たち体験者は子々孫々に伝えて、二度と過ちを起こさぬようにしなければなりません。
堀川 幸夫 私は昭和15年生まれなので、物心ついた5歳位の頃、今想えば昭和20年で、日本の敗戦濃厚、本土空襲を受け始めた頃のことである。当時は九州の佐賀市に居て、夜佐世保の方向の空が赤く燃え、大人たちが「サセボ、サセボがやられている」と叫んでいたのを憶えている。しょっちゅう空襲警報が鳴り、お寺の幼稚園から祖母に連れられて慌てて帰ったことや、夜には家の前の「どぶ川」に飛び込んだこともある。姉(富樫英子)は大事にしていた教科書を濡らしてしまったと聞いた。 しかし一番記憶にあるのは、食べ物に関することである。当時の日本はどこでもそうだったと思うが、自給出来るものは自分達で作ることであった。家の庭では鶏を飼い、卵を確保した。エサを刻んで与えるのは私の役目で、大きな雄鶏に追っかけられたこともある。又家の中には収穫したカボチャが天井から吊るされ、外では 安東 達 昭和20年4月、岡山市が空襲で焼野ケ原と化した。当時郷里津山に住んでいた私は、小学校6年生であった。午前3時、真昼のような明るさ、岡山から津山まで約70キロ、その間山あり谷ありの所である。終戦の1週間前B29が超高空を飛行機雲を引きながら1時間ほど飛んで南の方角へ去って行った。津山には工場としては、製糸会社「グンゼ」位なもので、米軍の目的は中国山脈の那義山の南の麓「日本原高原」に陸軍の飛行場があり、その撮影が目的であったと考えられる。その当時少年の私に理解できるわけがなく、後になって「そうか」と感じた次第。終戦の日の8月15日午前11時、ゼロ戦が超低空飛行で津山の上空を飛んだ。津山出身の航空兵だったのかもしれない。正午の玉音放送のことをすでに知っていたのか?午後1時、米軍の双胴の戦闘機ロッキードが同じコースを飛んだ記憶が、今も鮮明に残っている。
当時の小学生は、農家の手伝いに狩り出され、鍬を持参して畑を耕したり、草取り、田植え、稲刈の奉仕であった。空襲が激しくなった19年、小学5年生のとき、神戸から集団疎開で津山の男子小学校に、多くの同級生が移ってきた。神戸の空襲で焼け出された住民が海岸に避難したが、上空から機銃掃射を受け、多くの人が死亡した。弾丸と弾丸の間の距離は1m位で、次から次へ襲来、よく生き延びた、と話していた。
私の長姉の夫は近衛騎兵聯隊におり、終戦のとき近衛大尉であった。戦後は津山に帰り、銀行員になった。
広島に原爆が投下された後、学徒動員で近所に住んでいた方が後片付けに狩り出され、帰津後1ケ月で亡くなった。原爆の灰が原因だった。小学同級生の近所の友人の一人、父親は「三笠」の艦長だったが戦死。もう一人の友人の兄は陸士出身でこの方も戦死。
終戦になった2日後、米軍が装甲車を先頭に隊列を組んで日本原の飛行場に向かったのをよく覚えている。 神倉 孝夫 捕虜と楽しくキャッチボール 昭和20年の春、新潟県糸魚川市の父の実家に疎開中の私は、国民小学校の6年生。当時の戦争末期の生産力の困窮のためか、工場への勤労奉仕活動に動員された。
工場は隣町の青海町の、石灰石を採掘していた現在の電気化学工業・青海工場での作業。全身が、白い粉末に汚れる大変な労働だった。その中でも、今でも鮮明に楽しい記憶として残っているのが、一緒に作業していた白人兵捕虜たちと、昼休み中にキャッチボールをした一時の想い出。
陽気な外国人と初めて接した私は、こんないい人の国と、何故戦争しているのか不思議に思った。後日彼らは、B級戦犯に問われた日本兵が、死刑にまで処せられた直江津捕虜収容所の白人兵たちであったことを知った。複雑な気持ちであった。
中村幸子 (記憶)
私の一番古い思い出は、バクダンが落とされた甲府盆地が火の海となり、牛がモウ・モウと気が狂ったように走り回っていたこと。盆地が夕焼けのようにきれいだったのが・・・。
父は年令がいってからの召集で、年下の人達に軍隊でいじめられ、戦地から帰って来た時は風船のようにまん丸の顔になっていた(マラリアか風土病だったのではないかと思います)。周りの家々は全て焼かれ、我家はおくらに爆弾が土壁を破って突っ込んだまま、不発で済んでいました。兵隊さん2人が、取り出しに来て、運んでいったのをこわごわ見ていたのをおぼえています。甲府盆地を目ざして来た飛行機は、酒に酔いつぶれて明かりを暗くしていなかった坊さんの寺を、第1の目標としたそうです。
|
|
川和作二 炎天下に黒手袋と黒日傘 コスモスや微かな風も見逃さず 右赤城左榛名の青田道 栗原弘 老いの身に夏掛けさぐる夜明けかな 主なき家に盛りの百日紅 妻描く二個の無花果盆にのせ 杉野昌子 山宿の露天湯に聞く河鹿かな 暖かき緑茶の旨し夜の秋 静寂の夜半の目覚めや虫時雨 関口湖舟 炎天や田に立つ農の背のまろき かなかなの清らな音色位牌拭く 殊更に灯を消して見る今日の月 |
|
5月30日夜来の雨も晴れ上がり、薫風香る日和となりました。11時34分高尾駅前を、陣馬高原下行のバスで出発、窓外の風景は青葉若葉のしたたる山里と、北淺川の清流、源流に近づくと鱒釣場、約30分ほどで、夕やけ小やけふれあいの里」に到着。 りました。本殿の前には苔むした夕焼小焼の歌詞の大きな石碑がありました。 参拝を終えた後堀川さんの指揮で、童心に帰り全員で夕焼小焼を晴れた夏空に向かって合唱しました。石碑が建てられた場所に往時は社務所があり 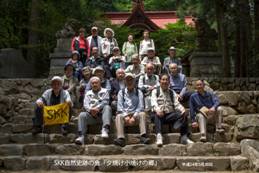 、そこで中村雨紅(本名 高井宮吉)が生まれた事を知りました。現在の宮司は高井住和さんですから、高井家が代々宮尾神社を守ってきた事がうかがえます。 、そこで中村雨紅(本名 高井宮吉)が生まれた事を知りました。現在の宮司は高井住和さんですから、高井家が代々宮尾神社を守ってきた事がうかがえます。 |
| あづま路 64号 | 平成24年1月 |
|---|---|
| 落合登美雄 | |
| 福島第一原発の事故と放射能汚染 | 藤井 清司 |
| 変わる結婚観 | 長坂恵美子 |
| 人生再考 | 二丸 雄策 |
| 第3章 日本の酒税の沿革と経済 | 安東 達 |
| 上高地奥飛騨散策の旅を終えて | 依田 武敏 |
| 姉とミュージカルに出演! | 堀川 幸夫 |
| |
東 隆昭 |
東日本大震災があってから九ヶ月が経過した。被災地は今、冬を迎え雪が降って寒い日が続いている事でしょう。被災地の皆さんに心からお見舞い申し上げます。
この人達が東日本大震災の被災地を回って現地に入った途端、実際に津波に流された町を見て大きなショックを受けたと同時に唖然としたようです。それ程までにすさまじい光景だったのです。この人達は 復旧、復興という道に 今年の漢字は「絆」である。人間はこの「絆」を強く持つ事が今こそ大切な事だと思います。私は最近、歌手の小金沢昇司さんの「ありがとう」という歌に興味を感じています。「ありがとう」という感謝の気持ちを常に心に持って人に接し、行動する必要があるとかねがね思っていたからです。歌詞の好きな部分を一寸披露しますと ありがとう、言いつくせない ありがとう 思い起こせば 数え切れない多くの人々に出会い 迷惑をかけたり 心配をかけたり 半人前の僕でした。 笑い合ったり 涙を見せたり 明日を信じて生きていける 兄弟、友人 ありがとう 勇気をくれたお父さん お母さん 感謝を込めて ありがとう あなたが居て 何時も見ていてくれたから.... ありがとう ありがとう。 と言った具合です。 不屈の精神と感謝の気持ちを常に念頭に置いて明日を、未来を力強く前進したいものです。 最後に、東日本大震災の被災者の方が早く復旧、復興を果たされて、元の生活に戻られる事を祈るものです。
|
|
はじめに 私が購読している週刊新潮には、「がんの練習帳」というコラムが、毎週掲載されています。筆者は、東大病院放射線科の中川恵一先生です。題名の通り平素は、色々ながんの最新治療法等についての紹介なのですが、5月26日号では、広島に原爆が投下されたときの被曝線量等の状況について解説があり、広島で被爆した私の興味をそそりました。やがて先生は6月に、「放射線のひみつ」という平易な本を、朝日出版社から出されました。これらの内容は、私が福島第一原発の事故のことを考える上で、非常に参考になりました。 放射性セシュウムによる汚染をどう考えるのか 福島の現場では、作業員の方々の奮闘により、事故は収まりつつあるようです。しかしその一方で、放射性セシュウムによる土壌等の汚染が、昨今の日本の大問題となってしまいました。マスコミが連日のように煽り立てるものですから、一億総ヒステリー症状を呈しているように見えます。これを解決するための政府の「除染対策」なるものは、地表近くの「汚染した土壌」を掘り起し、仮置き場を経て中間貯蔵施設に保管するという計画です。しかし汚染した土壌を化学的に処理できる目途はなく、このままでは右の物を左に移しかえるだけで、「除染」という命名には値しません。しかもこの作業には、膨大な人手とお金が必要なのです。 この問題について結論的に申し上げれば、セシュウムは無視しても差し支えないのではないか、と私は考えています。私に言わせれば、地方自治体も住民も、すべて騒ぎ過ぎです。子供を前面に押し出して、殊更神経質になっているように見えます。最近世田谷区で、高い放射能異常が検出される騒ぎがありましたが、長年床下のラジウムとの同居を続けていた女性には、何の健康被害もなかったという笑い話で済んでしまいました。一時はこれも福島の影響ではないかと、懸念していた学者先生も居られましたが。その後、同区のあるスーパーの駐車場でも同様な事件がありましたが、これらは放射能検知器が末端にまで行き渡ったことの影響である、と私は思っています。 チエルノブイリ原発事故による健康被害を調査された長崎大学名誉教授、長瀧重信先生によれば、現地では、放射性沃素に被曝して甲状腺ガンにかかった子供はいるが、放射性セシュウムによる健康被害は、1986年の事故から25年が経った今になっても、未だ認められていない、とのことです。しかし世の原発反対論者から見れば、このような冷静な議論は、到底容認し難いものでしょう。長瀧先生には、今はやりの「御用学者」というレッテルが、一部マスコミや「プロ市民」によって貼られているかもしれません。 他方、新たに放射性沃素が検出されたという報道は、最近は全く見られません。このことは、核反応が治まっていることを示しているわけですが、連日の過剰なセシュウム報道 -新たなホットスポットの発見等- のために、「福島の事故現場では、未だに新たな放射性物質が生成されつつある。」と、錯覚する人々も多いのではないでしょうか。
広島との比較 私は、広島の爆心地から約2km南の、舟入川口町の自宅で被爆しました。8月6日当日に私が浴びた被曝線量は、200ミリシーベルト(200mSv)前後と計算されます。ここで、話を正確に理解していただくために、中川恵一先生の著作から引用しておきます。 《「シーベルト(Sv)」という単位は、人体に対する放射線の影響度(危険度)を示し、「ベクレル(Bq/kg)」という単位は、ある物(飲料水、牛肉等)が持つ放射能の強さを示します。また、単にシーベルトと表記されている場合、それがSvなのか、それともSv/hなのかを区別する必要があります。更にシーベルトの場合には、単位表示に注意を払うことも肝要です。1シーベルト(1Sv)の千分の1が1ミリシーベルト(1mSv)、百万分の1が1マイクロシーベルト(1µSv)ということですが、うっかりすると単位を取り違えてしまいます。 医学の上では放射線の人体に対する影響を、「確率的」な影響と「確定的」な影響とに区分しています。放射線による「確率的」な影響とは、端的に言って「発がん」の可能性の増加を指します。放射線を受けたことにより遺伝子が傷ついて、がんの発生を招く恐れがあると考えられているのです。一方「確定的」な影響は、相当量の放射線を浴びたために、人体の細胞の一部、または多くが死ぬことによって起こります(細胞の多くが死ねば、人の死亡につながります)。これら二つの人体に及ぼす影響、「確率的」と「確定的」とは、はっきり区分して考えることが肝要です。》 私が8月6日に浴びた放射線量は、「確定的」な影響が生ずる可能性のあるレベルでした。とは言え私の場合は、髪の毛が抜け落ちたりするようなことはありませんでしたから、幸いにも「確定的」な影響は受けなかったということになります。一方今回の原発事故のために、「確定的」な影響を受ける恐れのある人々は、福島原発の従業員、作業員の方々です。これらの方々には、厳重な放射線測定と健康管理が必要です。但し、彼等の被曝線量は、あくまでも積算された累積の線量です。それに対し広島の人々の場合は、一瞬の間に被曝したわけですから、同じ数値であっても、両者の間には大きな違いがある筈です。 また、福島原発周辺の住民を含む一般の人々については、「確定的」な影響を受ける恐れはなく、「確率的」な影響だけを考えれば良い。また原発の作業員の方々の場合も、今後新たなトラブルに巻き込まれなければ、結果的には「確率的」な影響にとどまる筈です。ここでまた、中川先生の著作から引用します。 《人体に影響が生じ始める -発がんリスクの上昇が僅かながら認められる- 放射線量は、国際的には100mSvとされています。毎時11マイクロシーベルト(11μSv/h)の放射線を1年間被曝し続けると、この100mSvに達します。国際放射線防護委員会(ICRP)は、原発事故の際に許容される年間被曝量を、緊急時で20~100mSvに、事故の収束後は1~20mSvと定めています。今回政府はこれに従って、原発から遠く離れていても20mSvを超える恐れのある地域を、「計画的避難区域」として追加したのです。 このように100mSvという数値がひとつの基準になっていますが、「これよりも低い被曝量であれば、がんは増えない。」とまでは言い切れません。そのために20~100mSvとか、1~20mSvというように、警戒数値に幅を持たせているのです。》 このICRPによる警戒数値は、スリーマイル島原発事故以降の国際的な検討の結果を受けて作成されたもので、それなりの合理性を持っていると思います。しかしその一方で私には、これは机上の数字であって、日本の社会の実態に即したものではないと思えるのです。警報を発して一旦住民を避難させた後、事態が収束して、放射線量は年間20mSv以下の数値に落ち着いたとします。そのときに行政当局は、避難させていた人たちに対して「さあ帰宅しても大丈夫ですよ。」と、簡単に言えるのでしょうか。少なくとも日本の社会では、大変な議論が巻き起こります。行政側は、「安全になったから」と言いたいのですが、それに対し「プロ市民」の側から、「絶対に安全であることを証明せよ。」と反論されると、これに回答することは非常に難しい。「確率的」な影響ということは、何十年か先に発がんするかもしれないということだからです。 「絶対安全」を証明するためには、長い年月を待たなければなりません。この間、多くの人々の被曝線量を測定、管理し、個々人の健康状態を見守ることになります。そして何十年か後にある人が発がんしたとして、それが福島原発の事故に起因したものかどうか、疫学的に検証しなければならないのです。そんな気が遠くなるようなことを調べ尽くした上でなければ、避難措置は解除できないのでしょうか。 今現在も、強制的に避難させられている人々には、大変な労苦をお掛けしています。避難したお年寄りの中には体調を崩して、亡くなられた方々も多いと聞きます。一方、現実の放射線リスクは、取るに足らぬものです。マスコミにより毎日報道される各地の放射線量は、「確率的」な影響を及ぼす恐れがあるとされる100mSv/年(1時間値では11μSv)に比べて、一桁も二桁も低いものが大部分なのです。放射線リスクを避けんがために、反って健康被害を招いてしまっている現状は、正に本末転倒です。 原爆に被災した後の広島では、生き残った市民の多くは、損壊した家を修理してそのまま住み続けました。家庭菜園で採れたセシュウムやストロンチュームを含んだ野菜も、平気で食べていました。周辺の住民も同様です。人々は放射線のことは殆んど知らず、当局が避難を勧告することなど勿論ありません。今から思えば、「当時の日本国民は実に逞しかった。」と言うことも出来るのです。 私は、昨今の過度の放射能騒動の遠因は、近年の日本人の多くに見られる過剰な「健康志向」、そして「エコ志向」の風潮にあると考えています。これらの風潮は極めて自己中心的であって、現実を冷静に見据えることが出来ません。それが故に、日本国民の多くは短絡的になり、すっかりひ弱になってしまったのではないでしょうか。 近い将来、福島第一原発の「冷温停止状態」が達成されたとき、野田首相は蛮勇を奮って、直ちに避難地域の指定解除を宣言し、避難を余儀なくされていた人々が自由に故郷へ帰ることが出来るよう、措置するべきです。そして国民に対しては、新たな措置を決定するに至った根拠とその正当性を、自らの言葉を尽くして説明しなければなりません。それこそが真の「政治主導」というものです。 原子力発電の重要性 東日本大震災による福島第一原発の事故に加えて、前首相の菅某が、政権の末期に撒き散らかしてくれた数々の妄言のために、日本の原子力発電は、瀕死の重態に陥ってしまいました。日本の電力需給の混乱と不安定は、今後長期間に亘り続くことになりそうです。皆様方もご存知の通り、これまでの電力供給のベースは原子力発電でした。火力、水力発電所は、出力調整が比較的容易で需要の変動に対応し易いので、補完的な役割を担うことも多かったのです。菅妄言のために、全国の電力供給の大宗を成していた原発の多くが、運転停止の状態を余儀なくされてしまいました。 申すまでもなく電力が安定的に供給されることは、国民の生活と産業活動のために極めて重要であって、必要欠くべからざるものです。選挙の時には「国民の生活が第一」と唱えていた民主党は、政権を取った後では全く反対の事態を招いているのですが、何も反省していないようです。国民の多くも、菅某の口先三寸に乗ってしまって「反原発」、「脱原発」の風潮に染まっているように見えます。しかし常識ある人が考えれば、今の日本には原発が必要なのです。富樫さんが講演でおっしゃっていたように、風力も太陽光も、原発に取って代われるようなものではありません。原子力を中軸に置き、火力、水力を配することによって電力需要の大半を賄い、併せて地熱、風力、太陽光についてもその活用も図るということが、今の日本の現実的な姿なのです。 私自身は、定期点検を卒えた原発は直ちに再稼動させるべきであり、現在建設中のものについても、そのまま工事を進めるべきと考えています。前者の場合は、監督当局によって安全と認定されたが故であり、後者の場合は、経済的に見てその方が合理的だからです。それにつけても、定期点検終了後の原発の操業再開に際し、周辺の自治体が余りにも口出しし過ぎる現状は目に余るものがあり、悪しき民主主義の典型ではないか、と私は考えます(沖縄の基地問題についても似たようなことが言えます)。原子力発電以外に、日本の発電事業の根幹を担えるものは、当分の間あり得ないのです。 とは言え私は、今の原発の将来には疑問を抱いております。軽水炉に依存する原子力政策を、このまま継続することは問題である、と考えているのです。現在でも、使用済み燃料の再処理は大変厄介な事業であり、更にまた、最終的に蓄積される高濃度放射性廃棄物については、処分方法の目途も立っていないからです(今のところ世界のどの国でも、最終処分場はできていませんが)。このままでは徒に、危険なプルトニュウムが日本に溜まるばかりです。従来型の原発の建設を今後新たに計画することは、既に抱えている問題を一層増幅することになる、と私は考えます。軽水炉に代わる安全性がより高く、プルトニュウム生成量も少ない新型炉の開発が、早急に必要であると考える次第です。 (平成23年11月13日 記)
|
|
過日7月の定例懇話会では、先輩の方々の結婚のきっかけとなった出会い、交際、結婚へと、幸せな現在のご様子を聞かせて頂き大変参考になりました。有難うございました。 これをベースに、縁結びが業界と言われ、ビジネスとして華やかに世間に羽ばたく至っている今日までを、少し振り反ってみたいと思います。 1955年(昭和30年)殆どお見合い結婚、周囲の人々、
1970年(昭和45年)お見合いと恋愛の比率が逆転、お見合いの世話
1970年(昭和45年)この頃西ドイツからコンピュターによる結婚
1980年(昭和55年)結婚紹介業は大体4タイプに分けられる。
この様な状態の中で、結婚は決まるまでは密やかに行われてはいたが、何時の頃からか女性の意識は変わって、気が付いてみればお見合いも何時も女性本位に決まってしまっている。それは女性に海外出張があったり、旅行が当たり、残業、お稽古等々、多忙なのです。高学歴、高収入、高身長 男性の為にあった3高は今や女性にぴったりです。 男性の意識は、このような女性が多いので脅威であり、結婚しても今は一人で妻や子供を養えない。女性に働いて欲しいと言いたくないが、言わざるを得ない。男性はだんだん消極的になり、何となく先延ばししてしまう。最近は草食男子、[ 臆病で恋愛にも仕事にも消極的] しかし料理が出来る、育児には協力的、産休もとるし、優しい。何事も理解してもらえる。
キャリアウーマンにとっては釣り合いがいいと思うが、女性サイドから言わせると、やっぱり男性は「ばりばり仕事」をして「妻は家庭に」と言って欲しいそうだ。
2006年(平成18年)この頃から本屋さんに「婚活」という字を見か けるようになりパートナー探しが次第にオープンになっていっ 2008年(平成20年)婚活 巷でお見合いパーティ等が盛んに行われ る様に
2010年(平成22年)爺抜き、婆抜き 親との同居は頭から否定して
(三世代同居)頼るのは親、子供の利の為の発想であるとしても、 (核家族) 従来から伝わってきた親子関係は完全に崩壊、同世代 父親の存在が見えない。親が子供に気兼ねし、ご機嫌を取り、 少子化 子供の出生率 1974年 人口維持に必要な水準を下回り続けていた。 2005年 出生率は1.26を最低として上昇 2010年 1.33とアップしている。平均1.22と推定されていたが、想 2011年 少子化の原因とされている非婚、晩婚化が今良い方向に向 誰か側に居て欲しい。しかし問題は沢山ある。 |
|
現代社会はもろもろの効用もあって、平均寿命が長くなったというだけでなく、長寿に加え健康な老人が普通になった。65歳以上の年代を老人と呼ぶそうだが、70歳などは昔は古希、古来まれなる高齢と言ったが、今日ではたいして珍しいことではない。この年代こそが可処分所得と時間が一番多い、贅沢が可能な生きがいの多い世代ではないだろうか? 誰しも年はとりたくない。老いたくはない。誰しも必ず年をとり老いていく。 当たり前のことを、怯えたり腰が引けたりせず、正面きって向かい合い、こちらから仕掛けていけば、やり甲斐いき甲斐のある人生の時は他にない。 人生とは何か?誰もが考える果てしない問題である。だが余り早くから考えても年寄りじみて、日々の生活が楽しくなくなるのではないだろうか。私流の考え方では、人生とは精一杯いろいろなことやり、何歳になっても視点を変え楽しみ、限りなく夢を見て、これだと狙いをつけたものを実現させることでではないだろうか? 先人に学ぶ究極の人生論を紹介したい。 ゲーテ 徳川家康 福沢諭吉 一番尊いことは人の為に奉仕し決して恩にきせないこと。 一番美しいことはすべてに愛情を持つこと。 一番惨めなことは人間として教養のないこと。 一番楽しく立派なことは一生涯貫く仕事を持つこと。 荘子 小人は財に殉じ、君子は名に殉ず。 小人は財産や利益のためなら自分を犠牲にすることもいとわない。君子も 名誉や名声のためなら・・・つまり自分の個性を生かし自分を忘れず いつか学生時代の友人からの便りにこんな句がある。「五十、六十花なら蕾七十、八十働き盛り無常の風が吹いてくりや百まで行かぬと追い返せ」誠に痛快!ではないか。 さて「人の一生の禍福は糾える縄の如し」だろう。次々と織りなす禍福のアヤの中で人は喜び悲しむ。そして喜びと悲しみの連なる中に人生の歩みが後についてくる。そこで初めて人はしみじみと運命というものに気がつく。 数年前、後期高齢者に仲間入りしたが、老いを迎え討ち人生の成熟時代をさらに成熟させ、SKKで知り合った仲間たちよ、今後ともよろしくご指導を切にお願いしたい。人生を考える捨石としたい。 |
|
酒税法は極めて複雑であるが、明治以降の酒税法規の変遷を出来るだけ簡明に整理すると、別表に示すように、時代分類が出来る様に思われる。 第一の時期は1868年~75年(慶応4年~明治8年)の時代である。江戸時代の酒への課税は基本的に酒造家に免許税としての冥加金を支払はせるものであったが、明治に入ってもこの旧慣が受け継がれ、酒税は100石について20両という税額はその後金額は変更されるも、税の体系としては変更されなかった。 第二の時期は1875年~80年(明治8年~13年)。1875年10月に「酒類税則」が出され、二つの課税が行われる事に成った。酒造営業税(免許税)と、醸造税である。売り上げに対して課税するもので、当初は従価税であったが、3年後の1878年から従量税に変更された。 第三の時期は、1880年~96年(明治13年~29年)、酒の大増税が行われた時期である。明治政府の成立以来、財政赤字と貿易赤字の双子の赤字に苦しみ、財政補填と殖産資金捻出のため、不換紙幣の増刷を続けたために、明治10年代初めにはインフレに悩まされていた。それまで積極政策を推進してきた大隈重信蔵相は1880年に入ると、歳出を抑え、増税によって歳入増をはかる緊縮政策に転じた。この政策は明治14年の政変後、大蔵大臣に就任した松方正義によって更に強力に推進され、松方デフレが起こる事になる。 この増税で、酒は格好の対象とされ1880年に酒造税則が公布された。酒は酒造免許税と酒類造石税の2本立てで課税される事になったが、免許税は1878年の10円が3倍の30円に、造石税は清酒は1円が2倍の2円になり、大幅な増税であった。この時も酒造家の間で反対運動が起こったが、1882年(明治15年)再度、造石税の引き上げが行われるに至り、同年京都で酒屋会議が開かれ、強い反対運動が巻き起こった。このため政府は既存業者を保護する見返り策を提示、第一の策は造石高の下限を100石とし、第二は新規開業には既存業者5名以上の承認を必要条件とした、 第三は自家用酒も課税の対象とした。その後税率は何度も変更されたが、体系自体は1896年(明治29年)まで続いた。 酒税法が大きく変更になったのは日清戦争後の1896年(明治29年)のことである。日清戦争に勝利し、賠償金も得られたが、三国干渉があり、政府は対ロシア戦を想定、軍備拡張を進めようとしていた。その有力な財源が酒の増税であった。 第四の時期がこれに当り1896年に酒造税法が制定された。この時の大きな特徴は、従来の免許税が廃止され、造石税一本になった。更に重要な事は、日露戦争、第一次世界大戦まで、酒税は度々引き上げられた。増税のテンポという点では歴史上、最も早いものであった。又1901年(明治34年)には麦酒税が初めて導入された。1899年~1903年には、酒税が地租を抜き、国税のトップになった。この間の増税は様々な反対もあったが、見返り策として、既存業者の権益保護、造石制限の引き上げ、納税期限の変更、反則処分の強化、酒の鑑定官制度の導入等々で、酒税の徴税機構を整備.強化したのである。 度重なる酒税の増税が計られ、実現出来たのは「財政の玉手箱」と呼ばれたように、酒税が徴収しやすい税であったからであろう。当時の国税の中では地租が大きなウエーィトを占めていたが、帝国議会では地主が選挙権者であり、議員にも地主が多かった事から、地租の引き上げは政治的には容易ではなかった。酒造家も地主も地方の名望家が多かったが、この時代の酒造家の数は1万9千人程度、地主を相手にするよりは遙かに楽であった。 その後、1922年(大正11年)に未成年者禁酒法の制定、1938年(昭和13年)に酒類販売免許制が実施され、翌39年に酒類の価格統制が行われるようになり、税制自体が変更されたのは1940年(昭和15年)であった。 これが第五の時期である。従来の造石税に加えて、販売時にかかる蔵出税を導入した事である。蔵出税は毎年引き上げられ、1944年からの蔵出税一本となる。又1943年(昭和18年)から等級制が実施され、1989年(平成元年)まで続く事になる。 第二次大戦後には、税率がアルコール分、エキス分を中心として細かく限定され、従価税の導入も行われ、複雑極まる体系となった。1989年(昭和28年)酒税法は改正されるが、世界的に見ても相当高率な税となった。この間の特徴は、級別制度の強化、1968年、76年、78年と高級酒だけの増税が相次いで行われ,酒類間酒税の格差が相当の額となった。 この時期が第六の時期である。1980年代の中頃から、日本の酒税法に対してヨーロッパ諸国から批判が高まり、特に大問題となったのがウイスキーであった。ヨーロッパのウイスキーは原酒の混合率が高いので、どんな安いウイスキーでも特級扱いとなり、当時の国産2級ウイスキー 1リットルあたり酒税は296円であったが、輸入品の場合は 2,098円と約7倍になっていた。ECは GATTに提訴、1987年(昭和61年)
GATTは日本の酒税法の改正を勧告した。政府もやっと重い腰を上げ、1989年(平成元年)四月酒税法の改正に踏み切った。 第七の時期がこの改正時にあたる。1994年(平成6年)の改正は、ウイスキーと焼酎との税格差は甲類は4倍に、乙類は6倍に縮小された。1995年(平成7年)六月EUは日本の蒸溜酒の酒税格差問題を WTO(世界貿易機関)に提訴し、七月にはアメリカ.カナダも追従した。同年十一月 WTO は日本の酒税法は GATT違反と裁定、再度改正を迫られる事になった。1997年10月に第1段の改正、翌5月に第二段階の改正が実施され、ウイスキーの税率が劇的に下がった反面、焼酎の税率は相当額引き上げられる事となった。(別表参照) 表3 酒税法規の沿革
現行酒税法に規定されているもの (平成18年10月1日改正) *ビール 1kl 当たり \220,000 350ml缶 \110 1.発泡酒 麦芽の重量の1/2未満1/4以上 アルコール分10°未満 1kl 当たり \178,125 350ml缶 \62.34 2.発泡酒 麦芽の量 1/4未満 1kl 当たり \134,250 350ml缶 \46.99 3.その他発泡性酒類 ホップ又は苦味料を原料の一部とした酒類で以下に掲げる もの以外のものを除く ① 糖類、ホップ、水および政令で定める物品を原料として発酵させたエキス分2°以上のもの ② 発泡酒にスピリッツを加えたもの 1kl 当たり \80,000 350ml 缶 \28 *清酒 1kl 当たり \120,000 1,800ml 瓶 \216 *果実酒 1kl 当たり \ 80,000 720ml 瓶 \57.6 *ウイスキー1kl 当たり \370,000 37°未満700ml 瓶 \259 ブランデー *混成酒 1.合成酒 1kl 当たり \100,000 1.8l 瓶 \180 2.味醂および雑酒(味醂に類似するもの) 1kl 当たり \20,000 1.8l 瓶 \36 3.甘味果実及びリキュール 1kl 当たり \120,000 720ml 瓶 \166.67 (アルコール分12°1%増すごとに\10,000加算 4.粉末酒 1kl 当たり \390,000 *醸造酒 1kl 当たり \140,000 *蒸留酒 1kl 当たり \200,000 焼酎甲 乙 共 同一 (20°未満のもの 1% 増す毎に \10,000 加算) (次号連載)
|
|
ご参加頂けた方々の心掛けが良かったのでしょう途中にわか雨も降りましたが、歩いている間だけは一度も降られず、一言で云えば天候に恵まれた旅が出来ました。
集合時間の一時間前に新宿西口の集合場所に着き、観光バス、はとバス等が並んでいる所を歩いてみましたが流石にどなたも来ていませんでした。木曜日の朝7時半、早出の通勤の方々とバス旅行をされる方々が小さなグループを作っていました。まもなく栗原さん夫妻と堀川さんが見えられ、その後続々と皆さんが来て下さいました。8時半頃にはほとんど揃い、萩野さんを待つばかりとなりました。後で確認出来たのですが、別の道を通られ、すでに到着していらっしゃいました。 部屋に帰り幹事室で第2部が始まる。持ち込みのアルコール類ウーロン茶などで歓談する。男性群の一部はカラオケ室に、函館本線で使われていた客車2輛がホテル前に置かれカラオケ室になっている。11時30分でカラオケは終了、部屋に帰ってくると2次会も継続していた。2回目の温泉を楽しむ方もおり12時近くお開きとなる。 約1時間の見学時間をとり、北アルプスの山々を見る。遠い山々は薄い墨絵の如く、近く焼岳は見えたが、西穂高から北は山頂部が雲に隠れていたが西穂高山荘ははっきり確認
松本に入り、松本城見学。6層の松本城は国宝、旧のままの建物で、金曜日の午後2時~3時という時間帯なのに見学者は満杯、上り下りの階段が急で狭く、大変な大汗をかきました。
皆さん怪我もなく無事帰着、お互い家に着くまでが旅、気をつけてお帰り頂くよう願って解散となる。お疲れ様でした。
|
|
11月12日に、姉の富樫英子と一緒にミュージカル「オペラ座の怪人」に出演しました、とこう書くと皆様はびっくりされるかも知れません。 な!な!何だ? そのミュージカルってのは? 簡単に言えば、歌いながら踊る(いや踊りながら歌うのかな)演劇の一種であります。 題名を聞くとご存知の方も有ると思いますが、「ウエストサイド物語」や「サウンド・オブ・ミュージック」などがあります。 しかし最も有名で、今なお初演以来のロングラン公演を続けているのが、「オペラ座の怪人」です、昔流には、怪人は、「くわいじん」と読みます。 それはともかくとしてこの「オペラ座の怪人」は難解なストーリーにも拘わらず、世界 20ケ国で公演されるなど人気が高く、日本では「劇団四季」が全国各地で公演し、ロングラン23年目を迎えており、傑出したミュージカルと言われています。 姉と私は、或る合唱団に属していて普段は普通の合唱曲を歌っていますが、たまにこういったエンターテイメントに参加するのを楽しみにしています。 当日は顔にドーランを塗り、仮面を付けて踊りました、その時のコスチュームが写真の格好です。 |
|
|
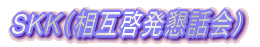

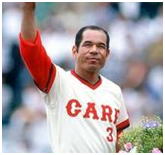 も休まず連続して出場したその連続記録は、衣笠選手が
も休まず連続して出場したその連続記録は、衣笠選手が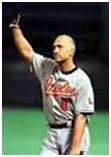 事に、感銘を受けたと語っている。そしてリプケンさんは、母親から何時も言われていた事がある。「もしあなたが、野球の世界で大きな影響を与えられる選手になったら、それを人の為に使いなさい」今回、野球を通じて日本の子供達を元気づけたいという思いがあった。小さい努力かもしれないが、沢山の笑顔に出会えたのは大きな喜びだった。日本の皆さんと絆を深める事が出来た。野球を教えるというのでは無く、皆さんと心を共有したと思っている。更に彼は、日本人から
事に、感銘を受けたと語っている。そしてリプケンさんは、母親から何時も言われていた事がある。「もしあなたが、野球の世界で大きな影響を与えられる選手になったら、それを人の為に使いなさい」今回、野球を通じて日本の子供達を元気づけたいという思いがあった。小さい努力かもしれないが、沢山の笑顔に出会えたのは大きな喜びだった。日本の皆さんと絆を深める事が出来た。野球を教えるというのでは無く、皆さんと心を共有したと思っている。更に彼は、日本人から 河童橋手前でバスターミナルに入り、徒歩で
河童橋手前でバスターミナルに入り、徒歩で 2150mの高知に降り立った。
2150mの高知に降り立った。